|
我が侭天使②
~第27代魔王温泉紀行シリーズ~

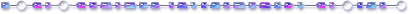
時を少し遡ろう。
つい先日、お忍び旅行に出かけた有利とコンラート(+ヨザック)は、鄙びた温泉町で《町興し》の為にと依頼されて《魔王陛下のふり》を頼まれたのだ。裏の裏は表とでも言うべき事態であった。
《魔王陛下が散策された道》《魔王陛下が入浴された温泉》などの名所を作りながら街を歩いていく内に、ひょんなことから有利とコンラートは互いの思いを告白し合うことになってしまった。
両思いとなった二人は王都へと帰還する道すがら、これからどうしていくかについて話し合った。
その時、有利の口から最初に出たのが《ヴォルフとの婚約を清算しよう》という案だった。
最初の出会いは最悪だったとは言え、今では掛け替えのない友であるヴォルフラムを騙すようにしてこっそり逢い引きすることを厭うたのだ。
それくらいなら喧嘩になるのを覚悟で正々堂々、正面切って恋仲になったことを伝えたい…。
『最近のヴォルフってさ、凄ぇ男前になったじゃん?きっと、ちゃんと話せば分かって貰えるよ。もともと、婚約者って言ってもチューさえしてないんだし、俺は何時だって《あれは文化の相違による誤解だ!》って主張してたしさ』
『そう…ですかねぇ……』
楽観的な有利に対してコンラートが半信半疑だったのは、やはり長年弟の性質を見詰めてきたせいだろうか?
直情型の愛すべき性質を持ってはいるが、それだけに…怒りが頂点に達すると社会規範よりも己の感情を優先させる傾向にある弟。
それが果たして、この3年の間に改善されているものだろうか?
『事が事だけに…難しいかも知れないな』
その疑念は見事的中してしまった。
兄としては哀しくなるほどの未練がましさに、有利に指摘されたとおり自分たちの教育が不十分だったせいなのかと反省もしてしまう。
* * *
「さあ、謝れ!」
「く…っ」
吊し上げを食らう小学生のような顔をして歯噛みするヴォルフラムに、有利はちょっと考えてしまう。
『うー…こんな公衆の面前でやんなくても良かったかな~…』
プライドの高いヴォルフラム相手なら、ひょっとすると密室対決にした方が良かったのではないか…とも思うが、今更だ。
案の定、ちらりと周囲を見回したヴォルフラムは顔を赤らめて、勢いよく立ち上がると手を差し伸べる有利の手を払った。
「ヴォルフ…」
「……謝るもんか!」
「えーっ?」
頑固に言い張るヴォルフラムに、有利はがっくりと肩を落としてしまう。
正直、彼がここまで頑なに勝負を認めないとは思わなかったのだ。
「ヴォルフ…俺に、お前を嫌いにさせないでくれよ…」
哀しげに言う有利に、ヴォルフラムは眦を吊り上げて抗弁した。
「お前に…僕の怒りが分かるものか!」
ヴォルフラムは謝らないまま踵を返すと、全速力で駆け出した。
「ちょ…ヴォルフ!?」
「旅に出る!」
追いかけて来る兄弟や有利を背にして、ヴォルフラムは厩舎に赴くと愛馬に跨り、荷物も持たずにそのまま綱を引いた。
「はいやっ!」
「ヴォルフーっ!」
かっぱかっぱかっぱ……
暴れん坊将軍よろしく派手な走りを見せながら、ヴォルフラムは去っていった…。
* * *
「ヴォルフラムめ…やってくれたな」
グウェンダルは頭を抱えて苦鳴した。
二人の弟が同じ相手を愛しただけでも問題なのに、よりにもよってその相手が当代魔王陛下なのだ。
長兄としての心情だけでなく、これは眞魔国内の権力分布から考えても重大な問題になる。
幾ら英雄と讃えられ、先代魔王の息子であったとはいえ、今日までのコンラートはいわば、一介の地方領主に過ぎなかった。それが、当代魔王の婚約者という立場を得ればその権威は飛躍的に増す。これまで血筋故に不遇に置かれてきた身が、本来あるべき栄誉に包まれることになる…とも言える。
だが、一方で収まりがつかないのはビーレフェルト家だ。
誇り高さというものが、この世で最も崇高なものだと思っている節のある一族のこと…ヴォルフラムが婚約を破棄され、代わりに据えられたのが混血のコンラートとなれば黙ってはいまい。
彼らはヴォルフラムと同一…いや、それ以上に自己中心的な価値観を持つ連中だ。
…であれば、ヴォルフラムの側から申し出た決闘を正々堂々とコンラートが受けた結果なのだとどれほど口を酸っぱくして言っても聞くものではあるまい。
『下手をすれば…内乱を起こしかねないぞ?』
決闘でヴォルフラムが男らしく負けを認める…。
おそらく、それだけがこの場を収める最上の方法だったのだ。
なのに、ヴォルフラムは負けを認めないばかりか、当事者達の前から姿を消してしまった。
これは、最悪の事態と言えよう。
「グウェン…怒ってる?」
「何のことですかな、陛下…」
「う…」
丁寧な口ぶりになるほど怒りを感じていると知っている有利は、肩を竦めて涙目になった。
『こいつは…きっと、ヴォルフラムがちゃんと決闘の結末を受け入れると信じていたのだろうな…』
グウェンダルとて信じたかった。
けれど…そうはならなかったことに、忸怩たるものを感じる。
『こいつが言うとおり、我々はあの子を甘やかしすぎたのかもしれない…』
天使のように愛らしい容貌と、神のように高い矜持…。
貴族らしい誇り高さや振る舞いは、見ていて心地よいほど鮮やかなものであった。
同時にその誇りは、その誇りが許容できないほどの事実は道理を曲げてでも拒否してしまうと言う諸刃の剣であった。それはもう誇りなどというものではなく、精神修練が足りないからこその稚気というものであろう。
それをどこかで、グウェンダルは愛でていたのかも知れない。
《この程度なら、可愛げで通る》《負けを無理に認めさせて、あいつの癇癪球が破裂するくらいなら、放っておいても良いだろう…》…決して、良くはない場面でまで、グウェンダルは大目に見てきたのではないだろうか?
そのような事実が降り積もって今日のような事態を招いたのだとすれば、グウェンダルにも責任はある。
「ど…どうしましょう!グウェン…!」
涙目になっておろおろと狼狽えているツェツィーリエは愛くるしく、肩を抱いて安心させてやりたいとは思うのだが…一方で、《この方にはヴォルフの教育に関する反省など無いのだろうな…》と、半ば諦観の混ざった眼差しを送ったりもする。
『そうだ…思えば、母上やヴォルフの我が侭や好き勝手を許容してきたツケは、私やコンラートに回ってきたのだったな…』
グウェンダルはまだ良い。だが…コンラートはどうだろう?彼は、一度たりと家族にそういった意味での愚痴を零したことはないが、混血として生まれた故に差別され、貶められる屈辱を家族の誰もが濯いではくれなかったのだ。
グウェンダルも影では色々と手を回したりしていたが、正面切って彼を擁護したことはない。
おそらく…有利だけだったのだ。
コンラートが当然受けるべき処遇を受けていないと憤ってくれたのは。
『貧乏籤を引き続けたコンラートが、初めて手にした当たり籤というわけか…』
いかに眞魔国の動乱を厭うグウェンダルとはいえ、二人の仲を引き裂く気には…なれなかった。
「ユーリ陛下、ウェラー卿コンラート…こちらに来ていただきたい」
「グウェン…?」
きょとんとする二人を部屋に呼び込むと、グウェンダルは意図を明らかにした。
* * *
『何処に行こう…?』
後先考えずに駆けだしたものの、宵闇が空を覆い、周辺の風景が濃い藍色に染め上げられるようになると漸く理性が戻ってくる。
ヴォルフラムは単騎でとぼとぼと草むらを行く。
かっかと頭に登っていた血が冷えてくると、色々なことが思い出された。
確かに…決闘を自分から申し込んでおいて、その結果を認めなかった態度は褒められたものではない。だが、ヴォルフラムにも言い分はあるのだ。
『僕だって…僕だって、ユーリを愛しているんだ!』
それだけを免罪符のように掲げてみせるものの、誰も当たる相手のいない平原でそんな世迷い言を信じ続けるのは難しかった。誰もヴォルフラムを怒らせてくれないから、実は英明な脳が理解していることがじわりじわりと頑なな心に染み込んでくるのだ。
『そんなことを言って…お前だって、前から気付いていたんだろう?ユーリはお前なんか愛してはいない』
『そんなことはない!だって、あいつは一緒の寝台に寝ていたじゃないか!あれを既成事実として何という?』
『既成事実だって?馬鹿を言うな。お前もユーリも、互いの身体には指一本触れて居ないじゃないか』
『……っ!』
それこそが、《婚約者》等という肩書きが仮初めのものであったことを物語っている。
口吻すら交わしたこともなく、《愛している》という言葉を一度たりと受けたことのないヴォルフラムが、有利の恋人などであろう筈がなかったのだ。
『でも…それでも…僕は……っ!』
有利の特別で居続けたかった。
せめて、《婚約者》という肩書きを持ち続けていたかった。
双黒の美貌と、それにそぐわないほど闊達な精神が、ヴォルフラムを魅了して止まなかったからだ。
『……軽蔑…されたろうか?』
初めての決闘の時も同じようにヴォルフラムは負けを認めなかったが、有利は呆れたように《えー?》とは言っても、その顔はどこか笑っていた。
《しょうがない奴だな》と、半ば呆れつつも《面白い奴》という顔をして笑ってくれたのだ。
だが、今回の有利に笑顔はなかった。
混血であり、魔力を持たないことが歴然としているコンラートに対して魔力をふるおうとしたことに心底腹を立てているようだった。
それだけ…有利にとってコンラートが特別な存在になってしまっているのだ。
コンラートの名誉を損ねることが、有利自身のそれを損なうよりも余程重大な問題として感じられるほどに…。
『嫌われた…?』
ぞくぅ…っと背筋が寒くなる。
それは、ヴォルフラムが初めて感じるような恐怖だった。
婚約者を奪われたという怒りよりも何よりも、もっと大きな感情であった。
気が付けばとっぷりと日も暮れて、初秋の夜風は肌寒さを感じさせる。
ガタガタと震えるほどではないが、それだけに…心に沁み込んでくるような寂寥感を覚える。
ふと…ヴォルフラムは陽炎のように揺らめく灯火を見つけた。
同時に、先程までは全く意識に登らなかった香りが鼻腔を擽る。
『…硫黄臭?』
微かな香りと独特の湿気は、ヒルドヤードで良く嗅いだもの…温泉の香りだ。
『こんな所に温泉街があったろうか?』
全速力で半日以上駆け通しに駆けてきたとは言え、王都からそこまで離れた場所ではない。名の知れた温泉街の筈はなかった。
もしかすると、隠れた秘湯なのかもしれない。
有利の影響でちょっとした温泉好きを自負するヴォルフラムは、疲弊しきった馬の鼻面をその香りの方向に向けた。
『もしかすると…温泉地でゆっくりしたら良い案が浮かぶかも知れない』
ヴォルフラムが頭を下げなくとも何とかなる方法…できれば、有利が想いを変えてくれる方向…。
今のところそんな都合の良い方法があるとは思われなかったが、何とか懐には銀貨金貨が入った財布もある。気分を変える為に逗留すること自体は問題がないことのように思われた。
『行くか…』
この時、ヴォルフラムは温泉地で何が起こるかなど予想することも出来なかった…。
* * *
『ヴォルフラムを探し出し、説得してくれ』
グウェンダルがコンラートと有利に依頼したのはその事であった。
二人にとっては依頼されるまでもなく、解決しなくてはならない重大事であったし、純粋にヴォルフラムの身が心配でもあったのだが、なにせつい先日まで休暇を貰って温泉地に逗留していた関係上、こちらから《追いかける》とは言い出しにくかったので、まさに渡りに船であった。
ただ、《婚約破棄されたヴォルフラムを捜す為に魔王と新たな婚約者が捜索を開始した》という事実が表沙汰になると外聞が悪いので、捜索の為の兵を指揮するコンラートも、随行している有利も簡単ながら変装をしている。
コンラートは目深にフードを被っているだけだが、有利は特徴的な双黒をいつもの鳶色の鬘とコンタクトで隠してから出発した。
グウェンダルは終始仏頂面をしていたが…出がけにコンラートの肩を引き寄せると、何事か囁きかけていた。
その時のコンラートの驚いたような…そして、はにかむように上気した頬から、グウェンダルが何を言ったかは有利にも想像はついた。
だが、面と向かって問うたりはしなかった。
兄弟には兄弟にしか共有できない想いがある筈。…そう思ったのだ。
だから、馬を走らせて暫くしてからコンラートが何気なく囁いた言葉だけで十分だった。
「グウェンが…俺達の関係を、祝福してくれたよ」
「そっか…」
心強いことだ。
そして…何よりもコンラートにとっては嬉しいことなのだろう。
『コンラッドは…さらっとしてるようで、本当は家族愛が物凄く深いんだよね…』
愛を得る為に藻掻くことに羞恥を覚えて自ら疎遠になっていた時期もあるというが、
きっと昔から大切で愛おしい存在だったのだろう。
『きっと、ヴォルフのことも凄く心配してるよね?』
どうしてもヴォルフラムの遣り口を糾弾したくなって声を上げたが、コンラートにとってはどうだったのだろうと今更ながらに気になったりする。
「あのさ…コンラッド。決闘の時に俺が出しゃばったこと…怒ってない?」
「何故俺が、怒るんです?」
「その…ヴォルフとの関係がこじれちゃったろ?」
「いいえ、あれはユーリが正しい。俺は…いや、俺達兄弟、家族は…ずっとヴォルフを甘やかしすぎていたんだ。あなたの仰るとおり…ね。それが良いことだとは思わなかったけれど、しょんぼりしているヴォルフというのはそれはそれは胃の腑に堪える図なものですから…」
「うん…それは俺も思う」
ついつい、こちらが悪いわけではないのに《ゴメンね》と言いたくなるような威力を持つのだ。
「ええ…だからといって、いい年をしたあの子をあそこまで聞き分けのない我が侭ぷーにしてしまったのは問題です。遅かれ速かれ…俺達は直面しておかなくてはならなかったのかもしれない」
「コンラッド…」
馬上で悲痛に眉根を寄せていると、《どうしたの?》と言いたげにノーカンティーが細くを緩めて軽く振り返る。その首筋を撫でつけてやりながら、コンラートは悪戯っぽく微笑んで見せた。
「それに…嬉しくもあったんですよ?俺の為に…あなたがあんなに怒ってくれたことは、それはもう…天にも舞う心地で嬉しかった…」
「コンラッド…」
「ユーリ…」
「ハイハイ、そこ…見つめ合わない。馬上で手を繋がない。危ないですよぅ~」
ヨザックに突っ込まれて二人は周囲を見回した。
共に走っている捜索隊の面々は、頬を染めてあらぬ方向を見たり何も感じていない振りをしながら瞑目している。
* * *
「全くもう。あんた達、もともとが恥ずかしいほどに仲良すぎるんですから、ちょっと周囲の迷惑も考えてセーブして下さいよ!」
「俺達の愛はそんなに迷惑なのか…」
「当てられちゃうって言ってんですよ。愛し合うのは結構ですけど、そりゃもーちょっと隠れてやってください」
「め…面目ない……」
ヴォルフラムと違い、自分の非についてはさっくりと認める有利はぺこんと頭を下げた。
その様子に、思わずヨザックの頬も緩んでしまう。
「全く…可愛らしいお方ですねえ。こんな愛くるしい可憐な方が、隊長のデカイ逸物を銜えてあんあん言わされるのかと思うと俺は目元に滲むものを感じますよ…」
《そりゃ幾ら何でも不敬過ぎだろう!?》…絶叫しそうになる兵達であったが、当の有利はきょとんとしている。
「コンラッドの何をくわえてあんあん言うの?マイク?」
旧ドラ○もんの代表的な主題歌を歌えと言うのか。
「ま…形状は似てますけどね」
ヨザックはにしゃりと嗤いながら意味ありげな眼差しをコンラートに送る。
この煮え切らないヘタレ男がよくぞ恋を自覚し、甘やかし放題の弟に対して宣戦布告なんて思い切ったことが出来たものだと感心していたのだが…どうやら、肉体関係の実情は何一つ進展がないものと見られる。
大方、《ヴォルフとのことがきっちり整理できてからレンアイはやっていこうぜ?》等と、爽やか~に恋人から言われたのだろう。
『こりゃ、責任重大だな…』
この様子だと、ヴォルフラムとの関係正常化が行われない限り二人の肉体関係はキス止まり…下手をすれば、それすらも阻まれそうな勢いだ。
『さーて、グリエ姐さんが一肌脱ぎましょうかね』
《ちょっとだけよ》…と囁きつつ、何をするつもりなのか…。
ヨザックはにやりと微笑んだ。
→次へ
|