|
~愛しのコンラート様シリーズ~
「魅惑のコンラート様」⑨
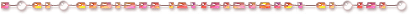
「せりゃぁああああああ……っ!!」
秋草を薙ぎ倒す勢いでマリアナの必殺技(意外と死傷者は出ない)が炸裂すると、女豹族の煙玉も発煙部分自体が吹っ飛んでしまう。
一気に開けた視界に勢いを増して、フォルツラント内に留められていた討伐隊員が駆け込んできた。どうやら騒ぎに対応できそうにもない馬たちは諦めたらしく、全員が徒地になっている。
「閣下…っ!コンラート閣下ぁああ…っ!!」
蒼白な表情で、絶叫を上げながら駆けてきたのは副官のイザークだ。
突然の襲撃によって分断された事を酷く恥じているらしく、コンラートの姿を認めるや、一瞬泣きそうな表情を浮かべていた。
「閣下…!ご無事でしたかっ!」
「ああ、何とかね」
「申し訳ありません…っ!」
グウェンダルやヨザックからも重々、《あいつを頼む》と言われていたし、イザーク自身も何を於いてもコンラートの身を護らねばならぬと思っていただけに、コンラートの優しい声が余計に身に沁みる。
しかし、コンラートの無事を確かめて心の余裕が出てくると、今度は別のものが気になりだした。
「こ…これは…っ!」
一体どこから突っ込めばいいのだろうか…?
まず、討伐隊が目標としていたはずの女豹族と思しき女達は、半数が大地に吹き飛ばされて膝を突き、もう半数は感嘆に瞳を輝かせながら両手を組んでいる。
一方、女豹族以上に怪しげな集団もいる。
いや、《怪しげ》を通り越して…寧ろどこからどう見ても《怪しい》と断言した方が良さそうだ。
そいつらは晩秋の折だというのに寒さも羞恥も感じないのか、紅い紐パン一丁の筋肉マッチョメンばかりであり、肌に塗ったオイルがてかてかしているので正直なところ取り押さえたくはないが…公共の福祉を考えれば、健全な一般市民の目には触れさせない方が良さそうな連中だ。
しかも、よく見ると全員見覚えがある。
『眞魔国の…それも、結構名の通った貴族ばかりじゃないか…!』
確か、熱狂的なコンラートのファンであり、《ウェラー狂団》とも呼ばれている宗教団体(?)に所属する坊主共では無かろうか?
しかし、彼らは滂沱の涙を流しながら四つん這いになっているので、討伐隊が力づくで取り押さえる必要はなさそうだ。どうやら、何かに激しく感動しているらしい。
《一体何に》…?と思って辺りを見回せば、何とそこには…秋草を絶妙な加減で灼いた《コンラート像》が広々とした平原一杯に広がっていた。
あまりにもでかすぎて、全体が確認できないのが非常に残念だ。ここに骨飛族がいたら、是非上空に吊り上げて貰いたいところである。
「ヒョォオオオ……っ…」
荒技を使ったせいだろうか?(そもそも、こんな人間世界のド真ん中で魔力など使った日には、疲労困憊して動けなくなるのが普通だろう)幾らか疲労を感じさせる呼気が、腹式呼吸でゆっくりと口から放たれていく。
その顔はえらく男前であり、纏うオーラのせいなのか…女性離れしたくっきりとした眉と引き締まった頬は、達人の域に達した武人そのものだ。
「あの方は…そのぅ……」
「ああ、ラダガスト卿マリアナ殿だ。女豹族を討伐して下さった」
では、討伐隊の目的は達せられてしまったのだろうか?
「は…っ!そ、そうだ…っ!お前達、責任者は誰だ!?ユーリ陛下の居場所を吐けっ!」
「まあ…ユーリ陛下ですって!?では、この者達は我が好敵手を強奪した悪漢ということですの!?」
怒りに目から火を噴きそうな勢いで、マリアナは女豹族の頭領の襟元を掴むと片腕で一気に釣り上げた。
「お吐きなさい…っ!さあさあさあ…っ!あの、お可愛らしいユーリ陛下に不埒な真似をするような者は、このラダガスト卿マリアナが許しませんことよっ!?」
「ぐ…ぐるじ…って、…ちょ…っ!そんなの…あたし達は知らないってばっ!」
信じがたいほどの力業でグラグラと宙に浮いた身体を振り回されると、舌を噛みそうになりながら頭領は苦鳴を上げた。
「まあ…そういえばコンラート様も、あまり必死になっておられませんわね?」
大したもので、マリアナはコンラートの気配から女豹族が有利を浚ったという疑惑が不確かなものであることに気付いた。
もしも本当に女豹族が疑惑の対象なのであれば、こんなにコンラートが女豹族に対して平和的な顔をしているはずがないのだ。幾ら相手が女とはいえ、血祭りに上げねば気が済まないという顔をするはずである。
『ちょっぴり…灼けますわね…っ!』
とはいえ、マリアナにとっても有利は全力で戦いたい敵だ。卑怯な手口で浚う者がいるのだとすればやはり許してはおけない。
「それでは…我が永遠の好敵手たるユーリ陛下は、いずこにおられますの?」
「俺もそれを知りたくて、待っているのです…」
顰められた目元に一瞬滲んだもの…その耐え難い苦痛と焦燥の色に、コンラートが平然とした風を装いながらどれほど追いつめられているのかが分かる。
『この方を…苦しめている悪漢がいるのだわ…っ!』
それはコンラートを愛するマリアナにとって、許し難い罪悪であった。
誇り高きラダガスト卿マリアナの辞書に《棚からぼた餅》などという文言はない。もとい…《食器棚からケーキ》という文言はない。
彼女にとっての至上命題は、コンラートが幸福であることだ。
勿論恋する乙女が持つべき当然の願望として、その横で微笑んでいるのがラダガスト卿マリアナであればとっても嬉しいだろうけれど…それは絶対的な要件ではない。それを達成する為にコンラートの幸福が瓦解するのであれば、グッと涙を呑んで堪えることが出来る。
それが侠(をとこ)というものだ…!
「ふぉおおおお……っ!悪漢め…出てらっしゃいっ!このラダガスト卿マリアナの究極舞踏によって、踵の錆にしてくれるわっ!」
ブーツの踵が錆びるかどうかは不明だが…取りあえず、先程の必殺技を目にした者が《あ、俺です》と自首することはまず考えにくい。
やはりこの場合も、犯人は恐れをなして自首してきた訳ではなかった。
「はぁ~い。ラダガスト家のお嬢さん、こりゃまた素敵な隊長像を刻んでくれちゃったもんですねぇ~。ここにも隊長マニアのお客さん達が参拝しちゃいそー」
不意に跳ね橋の向こうから現れた男は鮮やかなオレンジ色の髪の持ち主であり、袖無し隠密着の下から覗く筋肉が、マッチョ坊主達などとは比較にならないほど実戦向きの肉体であることを示していた。
尤も、この場にいた者で彼の肉付きに気を取られた者など皆無だったろう。人々の瞳は一心に、男…グリエ・ヨザックが宝物のようにお姫様抱っこしている少年に向けられていたのだから。
「…陛下…っ!!」
「まぁ…ユーリ陛下…!」
コンラート達が駆け寄るが、有利に反応は見られない。おそらく、薬か何かで眠らされているのだろう…不自然な睡魔に捕らわれた者独特の呼気がコンラートの胸を締め付けた。
「陛下…陛下……っ!」
「はいよ、たーいちょ…あんたが抱えてなよ」
ヨザックから有利の身体を受け取ると、コンラートは感極まったように《ぎゅう…》っと意識のない身体を抱きしめた。そうしていなければ、有利の身体が消えてしまうでも思っているかのように…。
「薬を…飲まされているのか!?」
やはり不自然な眠りに引きずり込まれているらしい有利に、コンラートは硬い声を漏らす。
「ああ、それほど強いもんじゃなさそうだけどな…」
「…本当か!?」
「直接聞いてみたら?」
そう言うと、ヨザックは背負っていた大振りな袋を大地に投げ出し、無造作に口を縛っていた紐を解いた。すると…中から出てきたのはフォルツラント公国の大公殿下であった。
何故だか蒼白な顔色をして、別に縛られているわけでもないのにえらく硬直したまま膝を抱えている。しかも、よく見るとじめじめとした涙を流し続けているではないか…。
「で…殿下!」
「貴様…っ!何のつもりでこのような無礼を働くか…っ!」
「……はぁ…?」
討伐隊に配備されていたフォルツラント兵が顔色を変えて詰め寄るが、蒼い瞳が凍てつく一瞥を送っただけで、目に見えて尻込みしてしまう。先程まで人好きのする笑みを湛えていた顔貌が凶悪なまでの険しさを帯びていることが、どのような意味を持つのか本能的に察したのである。
「何のつもりねぇ…。訳を言っても良いのかな?あんたらの大公殿下が、うちの大切な大切な…可愛い魔王陛下にやらかそうとした事をさ…」
「な…なにぃ…?大公殿下が何をなさったというのだ…!」
「朋友たるユーリ陛下に、耐え難い恥辱を与えようとなさったのさ。幸い、うちのお庭番のおかげで未遂だったけどね」
フォルツラント兵達に衝撃的な一言をもたらしたのは、小柄な少年だった。
だが、その背後から立ち上る瘴気は他を圧し、その華奢な体躯を倍にも見せていた。彼は…静かに微笑みながらも激しく怒っているのだろう。細いフレームの眼鏡を光らせながら、えらく陰惨な笑みを浮かべている。
まるで、漆黒の龍がそこにいるようだ。
「この男…ウェラー卿が兵を率いて出て行った途端、うきうき顔で自室に設えた仕掛け空間を開けて、隠していた渋谷を引き出していたんだ」
「天井が入り組んだ仕掛けになってて入り込めなかったもんでね、俺も華麗に登場…とは行かなかったんだが、何とか壁越しに会話を聞きつけたんで、思い切りよくお城に穴ポコを開けさせて貰ったよ」
こういう非常事態用の爆発物は、ヨザックの常備携帯品なのである。少々乱暴な手段ではあるが、まさに非常事態であったので許して欲しい。
「たたた…大公殿下!?」
「それは…真なのですか…?」
多少軽率な所があるとはいえ、概ね治世に落ち度もなく寛容な君主として知られていた大公は、意外に人望はあったらしい。兵達は《信じられない》という顔をして自分達の主君を見詰めたが、ツェルケスの方は茫然自失という感じで、周囲の状況が見えているとは言い難かった。
「ああ…ユーリ……私の天使だと思っていたのに…。あんな…あんなモノが付いているなんて……っ!」
「あんなモノ?蝙蝠の羽でも生えていたのですか!?」
「違う!それなら神秘的で余計に素敵に見えただろうさっ!うう…あぅぅう…っ!私の天使に、チンコが付いていたんだぞ!?これが嘆かずにいられるかぁぁあ…っっ!!」
「はぁ…っ!?」
兵士達は絶句し、コンラートやヨザック、村田…駆けつけたグウェンダルとヴォルフラムがびしりと眉間に深い皺を刻んだ。
「……大公殿下は成熟した女性には嫌悪すら感じるほどの、重度の幼女趣味であられるらしい。それが何を勘違いされたのか…うちの魔王陛下の女装姿を見て、《永遠の美少女》と思われたらしいのさ…」
「そーなんですよねー…。隠し空間に用意してた少女趣味のドレスやら淫具やらで、陛下を陵辱するつもりでいたらしいですよ。ところがどっこい…かそけき微乳はともかくとして、下半身の方は全くの想定外だったらしくってね?。着替えさせようとして紐パンに包まれた可愛いおちんちんを目にした途端に、一気に萎えちゃったと…そーゆーコトみたいですわ」
村田とヨザックが補足をすれば、辺りには何とも言えない気配が立ちこめる。
「なんという…っ!」
コンラートは怒りのあまり、ツェルケスを八つ裂きにせんばかりの気迫を見せて歯噛みした。すぐにでも怒りを形にして処罰してやりたい。言語に尽くしがたい苦しみを味合わせてやりたい…!
勝手な妄想を膨らまして有利の信頼を裏切ったばかりか、意識のない肢体を暴いて恥部を眺めるなど、到底許されるべき所行とは思われなかった。
だが…コンラートは眞魔国の兵だ。幾ら指揮官級の立場に就いているとはいえ、魔王陛下に従属する存在なのだ。それが…物理的な危害を加えていない以上、ここでツェルケスを叩き斬ることはできなかった。
「さーて…どういう処分が適切ですかね?猊下」
「渋谷が精神的苦痛を感じないやり方で、今後とも二国間の関係が悪化しないやり方…かな。それでいて僕達の受けた苦痛が昇華される方法…君、知らない?」
「どんなやり方でも、猊下が御納得されるとは思えませんがねぇ…」
「君もだろう?」
怒りに燃える肉食獣のような表情を交わしながら村田とヨザックが語り合えば、ツェルケスはやっと我に返ったようにぶるりと頬を震わせた。有利と国際関係の話を持ち出されたことで、漸く自分の立場というものを思い出したのかも知れない。
「わ…私一人の嗜好の問題でやったことなのだ…っ!どうか…フォルツラントとの関係は今後ともよしなにお願いしたい…っ!」
「君個人には、何をしても良いと言うことかな?」
「ひ…っ!い、痛くない範囲でお願いします…っ!」
肝が据わっているのか、とことん変人なのか…平身低頭して村田に謝罪しながらも、ツェルケスが心底反省しきっているとは思えない。もっと罪悪感が骨身に沁みて欲しいものだ。
「こんな男…っ!市中引き回しの上獄門送りに決まっているじゃないか!」
「落ち着け、ヴォルフラム!罪状を世界中に流布するつもりか!?ユーリが…魔王陛下が、《幼女》として辱めを受けるところであったと?」
「く……っ!」
ヴォルフラムの激昂を誰より理解しながらも、コンラートは鋭い語調で止めざるを得ない。
そのような恥辱を受けた有利がどれほど傷つくか…口さがない連中によって二次被害をこうむるかを考えれば、どうしても事件をそのまま公表することは出来ないのである。
「ん…」
コンラートの声に引き寄せられるように、有利が苦しげな息を漏らすと…彼の覚醒が近いことが知れる。
眞魔国の要衝達は蒼白になって身を震わせた。
事態をどう収束させるかが明らかになっていない今、目覚めた有利に何を言ってやればいいのか困惑していたのである。
普段はつるりと平気な顔をして嘘を付く村田ですら、顔を強ばらせて怯えたような目になっていた。
どうする…?
どうすれば良い…?
葛藤と焦燥の交差する茨を…突如断ち切るように、華麗な声が響き渡った。
「要するに、公的な処罰ではなく…眞魔国がフォルツラントを罰するという形式を採らずに、ツェルケス大公殿下個人に適切な刑罰を加えればよろしいのね?」
まるで《とっても簡単なこと》とでも言うように、彼女は確認した。
それを口にしたのが彼女でなければ…そう、疾風怒濤匍匐前進鼓腹撃壌なラダガスト卿マリアナでなければ、グウェンダル辺りが愁眉を顰めて窘めたことだろう。
だが…彼女が口にすると、《え?ひょっとして方策がありますか?》という気になるから不思議だ。
横紙を剣光一閃見事に断ち切るように、マリアナはこう言った。
「では、ユーリ陛下が受けたかも知れない陵辱を、ツェルケス大公殿下に受けて頂きましょう」
カクン…っと、ツェルケスの顎が下垂した。
「ま…まさか、この我が身を陵辱しようと言われるのか?あ…あなたが…っ!?」
ツェルケスの不躾な眼差しが上から下までマリアナの体躯を見定め、男装しているにもかかわらず全く隠し切れていない豊満な曲線美に泣きそうな顔になる。
ほとほと成熟した女性が苦手らしい。
「まさか!この私が…コンラート様への唯一無二の愛を貫く私が、貴様のような下賤の輩に身を投げ出すとでも…っ!?なんたる侮辱…っ!我が必殺技で大地深く沈めましょうか!?源泉を掘削しましょうか?油田を開墾しましょうか!?」
この女性が言うと、本当になりそうで怖い。
いや、見つかればちょっとした町興しになって嬉しいかも知れないが。
「いやいやいやいやっ!めめめ…滅相もないっ!」
「あなたのお相手ならば此この通り、適材がいるではありませんか?」
「……え?」
すっかり脇に追いやられていた女豹族の頭領は(実は先程からマリアナに襟元を釣り上げられたままであった)、不意に両肩を掴まれてズズイっと前に押し出された。
「さあ、好きなだけ子種を絞りなさい。遠慮無く。ギギュッと!」
手掴みで《ぐしゃり》と潰し、ねじ切る動作に…ツェルケスは反射的に股間を押さえていた。喩えでなく、物理的に陰嚢を潰されるように感じたのだろう。
「え…ちちち…ちょっとあんたっ!あたし達だってこんな野郎願い下げだよっ!あたしゃこんなゲレツ野郎の子なんか産みたかナイよぉお…っ!」
「盗賊の分際で贅沢を言うものですわね。では…好みの殿方と懇ろになって、懐妊が分かった段階で陵辱なさいな」
「えー?じゃあ…あっちの目がキラキラした旦那が良いなー」
頭領が頬をはにかむように染めながらコンラートを指さすと…
ド……ゴンっ!!
凄まじい速度で取り出された拳が、直接触れてもいないのに大地を陥没させる。
しかも、陥没痕が何だか焦げ臭い…。
どうやら、拳打の激しさによって大地が炭化したらしい。
「他の殿方になさい…っ!」
「ハ……ハイ……っ!」
鬼神の形相をしたマリアナに詰め寄られると(デスマスクを採れば魔除けになりそうだ)、頭領は背筋を硬直させて…声を裏返しながら承諾の意を示した。
→次へ
|