|
〜愛しのコンラート様シリーズ〜
「魅惑のコンラート様」⑦
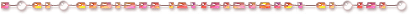
「まぁ…ここが女豹族が住むという山ですの?」
ラダガスト卿マリアナは抜けるような青空を背景に、高々と聳(そび)える峰々に目を見張った。秋口だというのに殆どの領域が雪に覆われ、険しい岸壁はとても馬が踏み込めるような場所ではなかった。
事情を聞いた狩人の親爺も、半ば呆れたように嘆息するのだった。
「お嬢さん…悪いこた言わねえから、その格好で山ん中に入るのだけはおよしよ。まー…格好がどうかなっても、そもそも女の身であんな山に登るなんざ自殺行為ですぜ?大体が、女豹族を退治するだなんてよぉ…何処の国の兵隊だって、這々の体で逃げ出すんぜ?」
トルソー山脈は広大な山岳地帯の総称であり、周辺国家との領土的な区切りは曖昧だ。特に何が採取されるというわけでもなく、勇猛な女豹族の住処になっているせいもあって近接した区域に住もうという民も国もないのである。よって、地理的な情報にも乏しい。
時折兎を捕りに行くという狩人に話を聞いたのだが、あまり重要そうな情報を聞き出すことも出来なかった。
それどころか、親切心から出たものではあろうがグチグチグチグチと説教臭いことこの上ない。
「もう結構!」
マリアナはここまで彼女を連れてきてくれた愛馬を撫でつけると、そのままスッタカスタカと歩き始めた。
帰還するのではない。当然、ここまでの進路と同様直線コースで突き進むまでである。
《前進あるのみ!》
《元気があれば何でも出来る!》
《振り向かない!それが青春っ!》
…これらがマリアナの座右の銘だ。
「や…待て待てっ!本当に危ねぇんだってお嬢さん!一人じゃあ…」
「《獅子は独り立つ》…ほほほ…コンラート様の座右の銘ですわ!」
勝ち誇ったようにマリアナは言う。
《だから何なんだよぉ…!》と、狩人は思った。
尤もな疑問ではあるが、ラダガスト卿マリアナには無意味な問いかけである。
「お…お嬢様ぁあああ…っ!ああ…ひぃ…ふぅ…っ!」
ひいはぁ言いながら駆け付けたのは、半分死にかけている馬丁と、馬車の中で揺られ続けたせいか流石に疲れの色は滲むものの、女主の為に尽くすことを至上命題としているメイド頭のシータであった。
「お嬢様…」
「まあ…シータ、あなたまで私を止めるつもり?」
「いいえ、滅相もない。ですが、貴婦人は腰を冷やすものではありませんわ」
「おお…そうね!」
す…っとシータが馬車の中から取り出したのは虎縞の華麗なマントである。
流石に真紅でこそ無かったものの、ふっさりとした大ぶりな毛皮のマントはマリアナの腰どころか踝までもある。
そのマントを宙に翻しながら羽織るマリアナに、シータはすかさず笛を吹き鳴らした。
ピピポ〜ピポピホ〜
ピーポーピーポーピ〜
ピピポ〜ピピピピポ〜
ピ〜ピポーピポピ〜
白銀の世界に打って出る女主人を高らかに送り出す曲目は、村田がいればきっと《初代タイ○ーマスク》の歌ではないかと誤解したに違いない。
まこと、不思議な偶然である。
「さあ…我が征(ゆ)くは愛の大海…っ!」
誇らかに告げるマリアナに、狩人は困り果てて《雪山だよぉお…っ!》と呟く。
都会のご婦人というのはこのように珍妙な連中ばかりなのか…と、狩人は死ぬまで信じ込んでいたという。
* * *
「なんだいなんだい…えらく珍妙な奴があたしらの縄張りに入ってきたじゃないか…」
「貴族の男の格好をしちゃあいるが…どっからどう見たって女じゃないか。何しに来たんだい?」
マリアナの奇行に呆れていたのは狩人だけではなかった。
近隣に住むことさえ恐れられているトルソー山脈に、一体何をしにのこのことやってきたのだろうかと、女豹族の面々は小首を傾げて針葉樹林の影からマリアナを眺めた。
「そういやぁ、昔にもああいう手合いがいたそうだよ?あたしのお袋が言ってた。恋人を捕られた女が取り戻しにやってきたんだってさ。こいつもそういう奴かな?」
「昔も今も変わんないもんだねぇ…。今回も騙りが出てんのかね?」
「それにしたって丸腰じゃないか。いくら剣に慣れてないお嬢様だからって、手ぶらで一体何しに来たんだって話だよ」
女豹族は呆れたように嘆息した。
確かに彼女たちは盗賊であり、秋の収穫時には食糧や家畜は有無を言わさず奪う。だが、男に関して言えばルール無用というわけではないのだ。好みの男を捕らえても、その男が恋人持ちや妻帯者であれば何もせずに開放しているのである。
ところが、彼女たちが大陸中で《種狩り》を始めると、どうしたものか常に何らかの形で便乗者が出る。
大抵の場合、それは貴族の男を陵辱することで都合の悪い縁談を破壊に持ち込む算段であったり、名誉を失わせることで失脚を狙う策略であるらしい。そういった連中は人間の盗賊団に話を持ち込んで、女豹族の格好をさせた女に目的の男を襲わせているそうだ。そういった連中の何人かが捕まったことで、《女豹族とは雪豹の耳と尻尾の剥製を身につけた女達》という認識が広まったようだ。
必ず女しか生まれないのと同様に、立派な耳と尻尾を持って生まれてくる女豹族にとって、これは甚だ不本意な噂であった。
だが、外部の世界と殆ど繋がりを持たない女豹族は、数十年前に勇気を持って婚約者を取り戻しに来た女の口から初めてそういった事情を耳にはしたものの、それでどうにかしようと思うには至らなかった(婚約者も女豹族が奪ったのではなかった)。
それが彼女たちにどのような影響を与えるわけでもないし…と、放置することにしたのである。
「ま…話だけでも聞いてやろうか」
女の身でここまでやってきた勇気は称えるべきだろう…そう思って頭領から留守を任されていたズーシャが一歩踏み出したが…次の瞬間、《ひゅ…っ》…と、つい先程まで視界の中で存在感を放っていた派手なマントが消えた。付き従っていた年嵩の女の姿はそのままであるにも関わらず…まさに先行していた若い女だけが《消えた》のである。
「…え?」
ズーシャ達の驚愕はそこに留まらなかった。
「あなた方が女豹族かしら?」
「……ひ…っ!」
突然、至近距離から聞き慣れない声を耳にしたズーシャが悲鳴を上げる。
ズーシャは女豹族の中でもかなりの腕利きで、年も重ねているから普段はかなり落ち着いていると自負しているのだが…自分でも驚くほど切羽詰まった声を上げてしまった。
それも仕方のないことだろう。
玲瓏な顔立ちの、如何にも育ちの良さそうな令嬢が一瞬にして自分の背後に回っていたのだから。
「い…何時の間に!?」
「つい先程ですわ。ほほ…囁き交わす声で、大体どの辺に居るかは察しておりましたのよ?ほほほほ…これも貴婦人の嗜みですわ」
どんな嗜みだ。
狩人がいたらそう突っ込んだかも知れないが、彼はここまではついてきていない。
村田がいれば《デ○ールイヤ〜は地獄耳〜》と歌ったかも知れないが、残念ながら彼も今ここにはいない。
そして、世間知らずな女豹族はころころと笑うマリアナの言葉にどよめいた。
「奇腐人のたしなみ…?」
「く…な、舐めやがって…っ!」
驚愕が抜けると、今度は激しい羞恥が押し寄せてくる。
どんな国の軍隊でも手玉に取れると自負していたズーシャにとって、自分のペースを乱されるほど腹立たしいことはないのである。
「掛かれ…っ!」
女豹族は原則として女は狙わない。食糧にする気はないし、嬲ったところで子種など取れないからだ。だが、今回に限っては自ら女豹族の怒りを買いに来たかのようなマリアナを、殺さないまでも痛めつけておかねば気が済まない。
この行動に、マリアナは不快げに眉を顰めた。
「まぁ…短絡的で野蛮だこと!」
「勝手にあたしらの縄張りに入ってきたんだ!それなりの落とし前はつけてもらうよ!」
「ああそうさ、丸腰だからってこっちゃ遠慮はしないからねぇ…!」
だが…女達の剣がマリアナの身体を打擲することはなかった。
「な…なにぃ…っ!?」
武闘派漫画のような集中線を放ちながらズーシャが叫ぶ。
彼女の閃かせた剣先に…何時の間に動いたのだろう?マリアナが爪先だちで乗っていたのだ。しかも、下肢を交差させて…っ!
「アンドゥトロア…!ほほ…コンラート様の為に磨き上げた舞踏の技がこんなところで生かされるなんて…!愛って素晴らしいですわ…っ!」
普通は生かされない。
舞踏で剣の先に乗る機会は多分無い。
だが、誰も突っ込む者は居なかった。
「さあ…我が愛のプレリュード……受けてご覧なさい!ふぉぉおおお……鮮紅鳳弾竜巻落としーーーっっっ!!」
炎の要素を従えるマリアナが優雅に両腕を振り上げていくと、その背後に逆巻く炎の粒子が巨大な鳳凰となって嘴を開いた。人間の世界…それも、氷雪に包み込まれたトルソー地区でこれほどの魔力を発揮できる者はマリアナを置いて他にはあるまい。
「うわぁああああ……っっ!!」
ズーシャ達の絶叫が連なる山並みに木霊した…。
* * *
「さ、よーく覚えておくのですよ?この凛々しいお姿のウェラー卿コンラート様を万が一にも浚うような事があってはなりませんよ?コンラート様の麗しきお姿に爪先で掻いた程度の疵を付けても、このラダガスト卿マリアナの蹴りがあなた方の土手っ腹を抉りますわよ?」
「は…はい……」
ズーシャ達は先生の言いつけを強制的に守らされる子ども達のように正座していた。
自分たちを一人残らずフルボッコにしてくれたどころか、ナイフで傷を入れることさえ困難な岸壁に、蹴り技の応酬で彫像など造られては抵抗する力も吹き飛ぶというものである。
寧ろ、いっそ清々しいほどの押し&腕っ節の強さに呆然としてしまい、たおやかに微笑むマリアナを神聖視する者も出ている。
ズーシャ自身、こてんぱんにやられたことですっかりマリアナに信服していた。
元々腕っ節の強さと狩りの腕が女豹族内での地位を決める大きな因子となっているのだから、多勢に無勢の闘いを制されたとあっては素直に頭を下げるほかないのだ。
「マリアナ姐さん…いっそ、ここで客分として暫く滞在なすっちゃどうですか?お頭が帰って来られたら、是非紹介したいんですが…」
「ま、責任者が不在ですの?そういう大切なことは先に仰い」
何時言う暇があったというのか。
流石に突っ込みたくなったが、怖いので止めておく。
「是非お会いしたいわ。やはりこういうことは頂点に立つ責任者に重々伝えておかなくてはなりませんものね」
「ね…姐さん!あたしがご案内いたします!」
「ほほ…気が利くこと」
マリアナに頭を撫でつけられたズーシャは、仔猫のように目を細めて悦びを示すのだった。
* マリアナ様、まずは女豹族征服。何やらコンユ再度との温度差が激しすぎますな…。 *
→次へ
|