|
~愛しのコンラート様シリーズ~
「魅惑のコンラート様」⑤
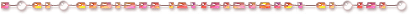
ゴトトン…ゴトトン……
見晴らしの良い平原を、秋草を揺らしながら精強な護衛団に守護された馬車が進む。
その様子を遙か彼方の断崖から…双眼鏡などの道具を一切用いることなく肉眼視している者が居るなどとは、おそらく想像もしておるまい。
《観察者》は集団であり、しかも肉感的な肢体に異色の《オプション》を纏う女性達であった。
そう…彼女たちこそは現在大陸中を騒がせている張本人、女豹族の一団だ。
「佳い男ばっかりじゃないか。目移りするねぇ…」
「あたしはあの、馬車の中にいる渋い男が良い」
「馬鹿をお言いでないよ。なるべく種は若い方が良い」
「じゃあ、あの真っ黒な子ども達かい?ご覧よ、言い伝えでしか聞いたことのない双黒だよ?種にも滋養があるんじゃないかい?それに、えらく可愛らしいよ」
「いや、あの金ぴかの子も良いよ。何て綺麗な子だろうね!」
馬車の中には彼女たちが好む《きんきらきん》の美形が鈴なりであった。掲げられた旗は彼女たちの知る何処の国旗にも似ていないが双黒が疎まれもせず美服を纏って尊重されているところを見ると、噂に聞く魔族なのかも知れない。
魔族の種だとえらく子どもが長命になるとは聞くが、彼女たちはさほどその辺りは気にならない。とにかく自分たちの腹から生まれれば、彼女たちは多少毛色の変わった子でも可愛がるのだ。
『あら…あの男、随分と良くないかい?』
護衛兵団は総じて優れた体格を持つ機敏そうな男達であったし、馬車の中には華麗な服装に身を包んだ高貴な男達もいて、女達は最初のうち目をにやつかせながらあちこち視線を彷徨(さまよ)わせていたのだが、そのうち…まるで示し合わせたかのように女達の視線は一人の男に収束されていった。
護り手である筈の騎士…凛とした佇まいの護衛兵団長らしき青年である。
「ふぅん…涎が出そうな程の佳い男じゃないか」
艶のある女の声が、実際に舌なめずりを絡めながら大気を揺らす。
ぱっと見た時にはついつい馬車の中の美麗な男達に気を取られてしまったが、あの青年…隙のない美しい所作や、ふとした瞬間にみせる艶やかな表情が何とも女心を擽るではないか。
一度気になると、目が離せなくなってしまう。
「確かにね。あの腰の張り…ありゃあ相当な動きを見せるよ?」
「子種も靱そうだ。沢山の女達を孕ませてくれそうだねぇ…」
今度は少し甘えたような徒(あだ)っぽい声が、やはり唇を舐めながら囁かれる。
実際、その男は彼女たちの目にえらく《美味しそう》に映った。
全員の目が、気が付いたらハートマークに象られている。
すらりとした長身は鞭のように撓り、馬上で揺れる様にも、川面で跳ねる若い魚のようなような柔軟さが見て取れる。広い肩幅と厚い胸板の割に腰は引き締まっており、その一方で腰の骨格はがっしりとしているし、そこから伸びる長い下肢は長靴を引きはがして舐めあげたいようなラインを描く。
襟足は短く刈り込まれているが、前髪は少し長めで時折切れ長の目元を掠めていく。
優れた視力を誇る女達の目には、その眼差しや顔立ちの凛々しさがくっきりと見て取れる。高い鼻梁…薄目の形良い唇、軍人にしては細い頤(オトガイ)。どれもこれもが涎を零しそうになるほどの男ぶりである。
そう、その青年とはウェラー卿コンラートのことだ。
彼は友人や兄、恋人の懸念通り…きっちりターゲットロックオンされていたのである。
「欲しいねぇ…」
女豹族は獣に跨ったままコンラート達を見詰めている。如何にも山岳の民と思しき鞣し革と毛皮を基調とした服装だが、その中で獣の形をした耳と尻尾だけが異彩を放っていた。
ただ…ふくふくとした雪豹の耳と尻尾が、獲物を見つけた獣そのものといった風情で揺れ動く様は、とても噂に聞くような《剥製》を身につけているとは思えない。
緑色に輝く瞳も何処か人間と言うより獣のそれを思わせ、ふとした瞬間に光が差し込むと《ひゅ…》っと光彩が縮む様子も猫そのものだ。
それに、彼女たちのしなやかにして豊満な体躯を乗せている獣は大型の雪豹だ。
自分達の身を包む毛皮を奪われているにしては…雪豹たちが彼女たちに寄せる態度は嫌々服従する家畜のそれではなく、仲間意識を伺わせるような親しみの色がある。
狩猟格と思しき野性的な美女…白銀の髪をきりりと頭上で結い上げ、一房を風に靡かせている女がするりと顎に手を回してやれば、良く人慣れした獣は野生を忘れたかのようにゴロゴロと喉を鳴らしている。
「お頭、行きますか?」
「ふ…ん……」
榛色の髪を短く刈り上げた女が囁きかけるが、頭領が間合いを取るように雪豹の顎から手を離して動きを見せようとした瞬間…馬上の青年がこちらを見た。
「…っ!」
思わず息を呑んだ首領の、蒼い瞳が見開かれる。
視線で射すくめられたかのように感じたのだ。
地形的に、平原を行く彼が断崖の木々に隠れた女豹族を視認するのは不可能な筈だ。
にも関わらず、青年の眼差しは何かを警戒するようにぴたりと女達の側に向けられ、手は柄へと掛けられている。
その身のこなしには一分の隙もなく、今襲いかかっても返り討ちに遇うのは必至であろう。幾ら精強を持って知られる女豹族とはいえ、警戒の度が強い警護兵団を屠るのは至難の業だ。
「ふん…面白いね。良い勘をしてる」
「どうします?」
「このまま後を追うよ。どこかで野営に入ったところを狙うんだ」
しかし、彼女たちはコンラート達の目的地がここからほど近いフォルツラント公国であるとは知らない。間合いを計っている内にコンラート達が堅固な防御壁の中に入っていったのを確認すると、臍を噛んで悔しがった。
それでも諦めはつかなかった。防御壁の中に入られたことでやりにくくなったことは確かだが、今期の《狩り》を一点に絞っても良いと思うほどコンラートは《美味しそう》な男だったのである。
頭領は鼻を鳴らすと、30人ほどの仲間を5つのグループに分けてフォルツラント公国の都周辺を周回させた。
『この国で生涯を過ごすって訳じゃないだろう。遠からず出てくるに違いない』
焦らされるほどに《狩り》は楽しい。
頭領はにやりと笑うと、印象深い青年の横顔を思い浮かべた。
* * *
フォルツラント公国の都スータンは眞魔国に比べれば小振りながらも、流石に国際的な催しを行うとあって、公的な建物だけでなく民家の殆どが統一性を持たせた装飾を施され、秋の装いに色づく街路樹や敷石にも様々な趣向が凝らされていた。
有利達を乗せた馬車が都に入ったのは夕暮れ時のことであり、街のあちこちにポウ…ポウっと明かりが点される頃であった。
色とりどりの硝子や梳き紙で造られた洋燈・灯籠は刻々と街の色彩を変化させていき、馬車が城へと到達し、宵闇が降りかかる頃には祭前夜のわくわくするような大気を湛えて、街中が明かりに包まれていた。
「ようこそいらっしゃいました!」
「お久しぶりです」
茶色い煉瓦造りの城も勿論沢山の灯火に包まれており、その明るさに負けないくらいの笑顔を浮かべて城の主…ツェルケス大公殿下が有利達を迎えた。
ツェルケスは三十路に入ったばかりの青年で、淡い亜麻色の髪を長く伸ばして一本の三つ編みにして背に垂らしている。これはフォルツラント貴族の習慣であるらしい。少し線の細い文芸好きのツェルケスにはよく似合っているので良いが、強面のがっちり型とか、ぶよぶよでっぷり腹の禿げ親父でも同じ髪型なのかと思うと少し可笑しい。
「おお…ユーリ陛下!月明かりに映える御身のなんと美しいことか…っ!その透き通るような象牙色の肌には、今宵の名月も自らを恥じて雲間に隠れてしまうやも知れませんな。それに、麗しきその瞳…澄み渡る夜空よりも深いその漆黒に、我が魂は吸い込まれそうです…!」
ツェルケスは眞魔国で開催された昨年の博覧会や、公的行事で何度か顔を合わせているせいか、有利に対して非常に親しみを込めた態度を取る。今も異国の要人同士が採るには些か問題を感じさせる距離に顔を寄せ、有利の手を取ると《我が国の挨拶ですから》と断ってではあるが…手の甲へと《ちゅ~ばっ!》っとばかりに随分ねっちりとした口吻を寄越す。
その間も、有利が困惑するほどの美辞麗句を並べ立てていた。
「ふぅん…渋谷、君の目玉はブラックホール並みの吸引力を持ってるみたいだね」
「…そんなタチの悪いもんなの?」
村田の言葉に有利がしょんぼりするが、それはツェルケスの勢いを留めるどころか先刻に倍する賛辞を呼び込むことになってしまい、眞魔国御一同を一層げんなりとさせるのであった。
しかもこの男、迷惑なほどに打たれ強い。
「申し訳ないが、大公殿下…うちの魔王陛下は大変な照れ屋なので、過度な賞賛の言葉を頂きますと萎縮してしまいます」
村田が眼鏡を輝かせながら笑顔で凄めば、眞魔国では大抵の者が遠慮するものなのだが…ツェルケスは大袈裟に両腕を開いて天を仰ぐと、芝居がかった動作で親指を上方に、人差し指を有利に向ける形に突き立てた。
《バキューン★》と擬音がつきそうな身振りである。
「これはこれは…私の愛の言葉にそのように照れてしまわれるとは、その愛らしさに乾杯!ですな。いやっはっはぁ…っ!こちらこそ照れてしまいます!」
ご丁寧に《バツン》とウインクに似た動作まで決めてくれる。
囂々(ごうごう)と吹き荒れる冷たい風にも負けず、ツェルケスの猛攻はその後30分間に渡って続けられた。
* * *
「全く…なんなのだあの男は!ユーリもユーリだ!あんな男に肌を赦すなど!」
「誤解を招く言い方すんな!手にチューされたり、肩抱かれただけじゃん」
「いーや!あれは立派な陵辱だ!ねっとりと舐め上げていたじゃないかっ!肩にしても、そのまま抱き竦めそうな勢いだったぞ?」
「よせよーっ!感触思い出しちゃうじゃんっ!!」
「ほら見ろ!お前だって自覚していたんだろうっ!?」
寝室を含めた個室は勿論一人一人に宛われているのだが、更に一室眞魔国御一同が揃ってくつろぐ為の部屋が宛われており、大公家主催の宴が終わった後のひとときをここで過ごすことになった。
そして、ぱたん…と後ろ手に扉を閉じるが早いが、ここまでギリギリのところで堪えていたのだろうヴォルフラムが撃ち放たれた矢の如き勢いで有利の襟元を締め上げた。
「ぐ…ぐるじい……」
「お止めよ、フォンビーレフェルト卿。多少馴れ馴れしくはあったが、大公殿下はフォルツラント宮廷に於ける礼儀を逸脱してまで渋谷に触れていた訳じゃない。責めるのは酷というものさ」
やんわりとヴォルフラムを制止するものの、村田の眉間にもどこか不機嫌そうな影が滲んでいる。
この少年はヴォルフラムと異なり、恋愛対象として有利を捉えているわけではないのだが…自分以外の者があまり馴れ馴れしく有利に触れることを好まない。
ましてや、有利自身が身の置き所がなさそうな顔で身体を強張らせていたりすれば尚更だ。
「そうだ、少し落ち着けヴォルフラム。ユーリ陛下のなさりようは、珍しくも一国の君主が友好国の大公殿下に向けるものとしては適切であった」
「グウェン…だったらどうして眉間の皺が深いんだい?」
コンラートがからかえば、《お前こそどうなのだ》と言いたげにグウェンダルの眉根が寄る。
実際、今宵の宴席に於けるツェルケスの態度は度を超した親しみ加減であったように思う。何かと言えば有利の身体に腕を回し、布越しとはいえ肌を撫で回し…しきりと語りかけては独占していたのだ。
眞魔国の要人達は一様に笑みを湛えていたものの、やはり一様に臓腑の中で煮える何かを感じていたのだった。
有利だけは多少の戸惑いを感じていた程度だったようだが、それも物言いたげなコンラートと目が合う時には《ゴメンね…》と淡く翳っていた。
コンラートは滅多に有利を独占することはなく、こうして弟が我が物顔で想い人を締め上げていても笑顔を浮かべて見守っている。けれど時折…堪えきれなかったように閃く瞳の切なさに、有利も気付くようになっていた。
『《誰にも渡さない…!》なんて、あんな席じゃあ流石にヴォルフだって言い出さないもんな』
ツェルケスの態度は《無礼》に当たるすれすれの所で《屈託のない親しみ》の範疇内にとどまっていた。それだけに、誰も止めることが出来なかったのだが…。あまりそういった接触に頓着しない有利でさえ、少し不審に思ってしまうくらいのはしゃぎようであった。
「ツェルケスはまだ若いし、こんなに大規模な国際行事をやんのは初めてらしいもんな。ちょっと…躁状態なのかも」
「ま、そうなのかもねぇ…」
適当に相づちを打ちながらも、村田の口調は何か含むものを持っているようだ。
まぁ…この少年が腹に何も持たず事に当たることなど滅多に無いわけだが。
「とにかく、博覧会をめいっぱい楽しんで帰ろうぜ?面白い発明品とかあったら、アニシナさんの為に詳しい話を聞いて帰ろうな」
「不吉なことを言うな」
敢えて明るく有利が言うものの、間髪入れずにグウェンダルが苦言を呈する。
それでなくとも面倒なあの女性を刺激してくれるなということであろう。
何はともあれ、有利達は過剰なまでのツェルケスの歓待を受けながら博覧会を迎えることになった。
* 久し振りなのでちょっとペースが掴めませんが…。早くマリアナ様で勢いをつけたいです。 *
→次へ
|