|
「君が欲しい」−2
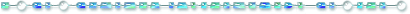
「お…俺、謝んないからな?」
「何のことでしょう」
ホテルの部屋に戻ってくると、緊張しきった有利とは対照的に、コンラートはしれっとした顔をしていた。いつも通りに室内のチェックをして、異常がないことを確かめると玄関に近い扉に右肩をそっと沿わせて立つ。
ボディーガードとしては無駄に綺麗すぎるその容貌は、素っ気ない仕草さえも映画のワンシーンのように見せていた。
『……根に持ってるな…これは』
出会ってすぐのことならば、《意外と気にしてないのかな》とでも思ったことだろう。しかし、なんだかんだで数ヶ月も過ごす内に、幾らかコンラートのことが分かってきた。
この人は誤魔化したいことがある時ほど無表情になるのだ。
ただ、そこを指摘してしまうのは勇気が要ることだ。
敢えて平静を装っているというのに、そこを突かれたりすれば逆鱗に触れてしまう可能性がある。
それでも、ちゃんと言葉で分かり合いたくて…有利はごきゅりとつばを飲み込むと、意を決して口を開いた。
「…コンラッド、あ…あのさ?俺って、あんたに恋人って思って貰ってるの?」
言った途端にかぁあ…っと血の気が上がってくるのを感じた。《恋人》という単語は、年頃の少年が使うには何ともハードルの高い言葉なのである。
「どうでしょうね?」
くす…っとコンラートは意地悪に嗤う。
これは相当機嫌を損ねているらしい。
「あなたこそどうなんです?恋人かどうか問いただしたい男の前で、堂々とデートの約束をしたくせに」
「俺は、あんたに恋人って思って欲しいよ。だから秋津さんとの約束もあんたの前でしたんだ。後ろめたい事なんて何にもないって、分かって欲しいから」
「…」
コンラートはすぅ…っと表情を消すと、殊更ゆっくりとした足取りで有利に近寄ってきた。ソファから立ち上がって拳を握っていた有利は、懸命に表情を整えてコンラートに向き合った。
無理な背伸びをしていることは分かる。
それでも、コンラートに対等な相手として見て欲しかったのだ。
「自分の言葉に、責任を持てますか?」
「持ちたいと思ってるよ」
「まるで政治家の答弁のようですね。やる気があれば、結果的に達成できなくても意義があると仰りたいので?」
「……っ!」
言葉が、上手く噛み合わない。
もどかしさのせいか、喉奥にグ…っと込みあげてくる物を感じた。
『どうして分かってくんないの?』
有利はコンラートが大好きだ。
時々大人げないけれど、彼には言葉以上に通じ合う何かを感じる。それは突然の環境変化に戸惑っていた有利にとって、得難い落ち着きと喜びを与えてくれるものだった。
でも…今のコンラートには何を言っても空回りしてばかりだ。
「俺は、あんた以外の誰にも…そのぅ…こ、恋なんてしないよ?特に男が相手だったら、普通は《好き》って感じるのは友情とか尊敬の意味でだろ?俺はあんたを恋人にしてるけど、だからって他の男の人と仲良くなっちゃ駄目って事はないだろ?」
そうでなくては、有利は社会的の繋がりが希薄な人間になってしまうではないか。
恋人としての愛情は誰かと共有することが出来ないけれど、友情や尊敬の気持ちは多くの人と分かち合いたいのだ。
「どうだか…」
鼻で嗤われるのが、酷く胸に痛い。
「あなたは押しが弱いところがあるから、ある程度好意を持った相手に切々とかき口説かれれば、結構絆されてしまうんじゃないですか?」
「……っ!」
振り上げた手は、簡単に片手で止められてしまう。
「申し訳ありませんが、俺はどちらかというとマゾヒストよりサディストの因子が強いので叩かれるのは御免です」
「知ってるよそんなのっ!」
子どもみたいにじたばたしてもう一方の手も伸ばすけれど、これも易々と捉えられた上に唇も塞がれてしまう。
「ん…ぅ……っ」
こんなキスなど許し難いのに、きっちりと噛みしめていた筈の唇は、巧みな舌遣いによって陥落されていく。
数分の後には息が苦しいくらいに煽られて、甘い息を漏らしているのがどうにも悔しかった。
「ほらね…こんなに簡単に籠絡されてしまうあなたを、どうやって信じろと?」
皮肉げな囁きが毒のように耳朶へと注ぎ込まれ、唇の端をカシリと痛いほどに囓られるから、精一杯の力を込めて睨み付けたのだけど…有利ははっと胸を突かれたように息をのんだ。
コンラートの瞳が、軽蔑よりも哀しみを滲ませていることに気づいたからだ。
『コンラッド…もしかして、不安なのかな?』
転がされているのは自分の筈なのに、何故かそんな風に思ってしまう。
コンラートは有利を信じ切れないというよりも、信じて裏切られるのを恐れているようだ。だから、最初から期待してはならないと自分に言い聞かせているのではないか…そう思うのは、自分に都合の良い妄想なのだろうか?
いや、でも幾らか信憑性もあるのだ。
以前、有利が浅葱という少女(?)達の組織に財産を狙われた事件の時に吐露してくれた心情は、彼が自分でも処理に困るくらいの嫉妬心を抱えているということだった。
それだけ、有利に固執している事実を認めたくなくて…それでも、惹かれるのだと苦しげに言っていた。
『でも、やっぱ俺はこの人に信じて欲しい』
コンラート以外の誰とも深く付き合わないのではなく、多くの人の中から彼を選びたいのだ。
「コンラッド…!ね…聞いて?」
有利の出した提案にコンラートは一瞬珍妙な顔をしたが、どう思ったのかは不明なまま…一応は容認してくれた。
* * *
「シンデレラボーイの有利君ねぇ…」
もう深夜を回って日付が変わってしまう時分だが、秋津は何やらわくわくしてしまって、ちっとも自宅に帰る気が起こらなかった。有能な秘書がユーリ…渋谷有利について調査して、その報告書を手渡してくれたからだ。
ピュウ…っ!
佐々野の纏めた報告書を片手に、秋津は楽しそうに口笛を吹いた。
「社長。夜中に口笛を吹くと蛇が来ますよ」
咎めるように佐々野が銀縁眼鏡を引き上げるものだから、秋津は叱られた子どもみたいに唇を尖らせた。
彼は必要に応じて顔を変えられる男だが、それにしたってこんな表情が似合う男がもうすぐ40歳というのはどうかと思う。
「佐々野…お前さん、時々もの凄く年寄り臭いことを言うよね…。実はトシ誤魔化してない?」
「男がサバ読んで得する事なんてないでしょうに」
一応、佐々野は秋津より5歳ほど年下だ。
「そりゃそうだ」
ため息混じりに肩を竦める部下に対して、秋津は労うように肩を叩いた。
「それにしても…手元にあったのは公園で隠し撮りした写真だけだったのに、よくここまで短期間に調べられたものだね。我が秘書ながらちょっとコワイくらいだ」
「写真など無くても調べられましたよ。権現財閥の遺産を血縁関係のない男子高校生が引き継いだという話は有名ですからね。それに、あの護衛も相当名の知れた男です。顔を少し見てピンと来たんですよ」
「へぇ…」
頼まれたわけではなかったのだが、佐々野はついでにコンラート・ウェラーについても調べてきた。
シークレットサービスの凄腕であったダンヒーリー・ウェラーの息子にして、《氷の刃》の異名を取るクールビューティー…雇い主をその気もないのに次々と虜にしてしまい、言い寄られた挙げ句片っ端から冷たくあしらって契約を切るという、曰く付きの男である。
「おー、写真越しでも迫力のある美形だねぇ。恋のライバルとして、敵に不足無しって感じだな」
「あなたの方に不足があるとは思われないんですか?」
「私は自分の価値をよく知っているもの」
くすりと悪戯っぽく笑えば、佐々野は呆れたように溜息をつく。
だが、その表情は本人が醸し出そうとしているほどには嫌みなものになり切れない。
実際問題として、優秀だが癖のある佐々野が同じ職場に長年務めていられるのは、やはりこの社長の力量と人格の《おかしみ》を愉しんでいるからだ。
「良くも悪くも、あなたは日本人離れしてますよね」
《少しは謙遜という言葉も覚えてはどうか》と言う嫌みのつもりだったのだが、分かっているのかいないのか…秋津はさらりとポジティブに受け流す。
「おやおや、そんなに日本人を見下げたものでもないよ。有利君みたいな撃墜王(エース)もいるしね」
「ま…確かに渋谷君に関わっている相手の顔ぶれを並べると、大したものだと感心しますよ。見た感じ、可愛いけど普通の子なのにな…」
佐々野は不思議そうに小首を捻った。
偏屈で知られた《巌の権現》こと権現源蔵の遺産を継承し、《氷の刃》と呼ばれるコンラート・ウェラーを恋人に持つ男子高校生は、今度は衣料業界にその人有りと知られた《トリスタン》の社長、秋津玲治を魅了してしまったのだ(それも、タイ焼き一匹で)。
大手アパレルメーカー《トリスタン》は大学卒業直後に秋津玲治が立ち上げたもので、設立から僅か数年で世界進出を果たした上、この冷え切った経済状況の中にあって業績が常に右肩上がりを続けている奇蹟の企業である。
元々秋津自身は大手建設会社の四代目として何不自由ない生活を送っていたのだが、会社の立ち上げに当たっては、業界違いということもあってその力は殆ど借りていない。今では、親親戚の全ての企業を併せた資金力をも上回っているのだから、《親の七光り》との言葉は当てはまらないと思う。
トリスタンの商品は唯安いと言うだけでなく、デザイナー、特殊素材の開発者、縫製担当者等々が実に有機的に結合することで巧みに顧客心理を掴んだ付加価値を付け、投げ売り競争に待ったを掛けているという点でも、業界では大いに注目を浴びている。
その原動力となっているのは何と言ってもこの秋津玲治という社長の力量にある。
彼自身はまち針を爪と肉の間に刺してしまうような男なので、服飾の才能はとんと無いのだが、とにかく楽しいことと《人》が好きなのである。
《これは面白い奴だ》と思ったらテコでも引かずに掻き口説いて陣営に引き込んでしまうのだが、その人選は勘でやっているとは思えないくらいに的確であり、常に会社内には良い意味での新風が吹き込んでくる。
その秋津の目に敵ったというのなら、渋谷有利にもそれだけの価値があるということだろうか?
この男のことだから、《持参金》に目が眩んで…という事ではないと思う。
金というのはあくまで《天下の回りもの》だと素で信じているようだから、どこからか不正な金をせしめてこようというような、けちな了見は持たない男なのだ。
佐々野は別にゲイではないし、少々変人気味な社長を如何なモノかと思うこともあるのだが…そういう点は素直に尊敬できる。
「で、どうなさるんです?」
「んー?まずはデートでしょ」
学生服姿の有利の写真にキスをする様子に、佐々野は軽く胸灼けの様な感触を味わった。
『こういうとこさえなきゃ、いい人なんだけどねぇ…』
嗜好の問題なので、深くは責められないと知りつつ…そっと溜息をつくのであった。
* * *
「秋津さん、お世話になります」
「失礼する」
次の週の日曜日の夕刻の公園…。
秋津玲治は視界に飛び込んできた映像に苦笑した。
約束通り、有利は来てくれたのだが…瘤も付いてきてしまったのである。
有利は暖かそうなニットの服を着込んでいるのだが、心なしかぷるっと肩を震わせていた。
周辺空気が一度以上下がりそうな冷気を漂わせて、憮然としたコンラートが腕を組んでいるせいではないかと疑惑が持たれる。
「…では、とっととデートをしてください。俺は横で見守らせて頂きますから」
「そう〜?見守っちゃう〜?」
からかうような口調は、どこか楽しげである。
ひょっとするとコンラートがやってくることを予想していたのかも知れない。
「…主のご命令ですから」
「そ〜?意外と忠実だね、君…」
「ええ…主が無防備で天然な赤頭巾気質なもので、餓えた狼に食べられないよう、見守る必要があるのでね」
「ふ〜ん?君の冷気に侵されている有利君を、是非毛皮で包んで暖めてあげたいところだけどね〜…人肌程度に」
コンラートと秋津の嫌み合戦は放っておくと何時までも継続してしまいそうだったが、そこは慌てて有利が止めた。
「あ…あの…っ!秋津さん、俺がコンラッドに頼んだんですっ!一緒に行こうって…」
「そうなの?」
有利の言葉に、秋津はしょんぼりと肩を竦める。
「君も私のことを餓えていると思うのかい?確かに、隙があれば私の懐で暖めてあげたいと思っているけど…嫌がるのを無理矢理押さえつけたりはしないよ?何処かの誰かみたいに」
「……見たようなことを言う」
「おや、図星?」
コンラートの眉間には、深々とした皺が刻まれた。
これでは全力で頷いているのと同じである。
「そ…そーじゃないんですっ!俺…秋津さんのこと凄く感じのいい人だと思ってるけど、それはその…あ、あの…二人きりでごにょごにょ…したいとかじゃなくて…普通にお話ししたいりしたいんだって、コンラッドに分かって欲しくて…」
有利の説明は些か不明瞭なものではあったが、秋津には十分に伝わったらしい。
「ああ…うん。言いたいことは分かるよ。そうだね…まずは、私のことを知りたいと思って貰ったことに、礼を言わないといけないね」
ふわりと微笑んだ秋津は、諍いの気配など綺麗に鎮めて有利とコンラートを促した。
「さ、まずは君が期待していたたこ焼きを食べないかい?」
公園には先程からたこ焼き屋の屋台が入っており、丁度美味しそうな香りを立てて焼いているところだ。
「コンラッド、たこ焼き好き?…あ、食べたこと無いかな?タコ平気?」
「タコは別段嫌いではありませんよ」
欧米人の中にはタコやイカを《気持ち悪い》と毛嫌いする者もいるようだが、取りあえずコンラートは平気らしいと聞いてほっと胸を撫で下ろす。
じゅうじゅうと香ばしいかおりが漂うのと、おじさんの華麗なピック捌き(?)を眺めていたら、変に緊張して昼食をあまり食べられなかったものだから(なにせ、ガチンコ勝負を控えていたので…)、えらくお腹が空いてきた。
「わーい。焼きたてだ〜…美味しそう!」
「そうそう、たこ焼きは焼きたてに限るよね。外はかりっとしてて中はジューシーなタコの出汁が溢れてくる…ってのが最高だよ」
うきうきしてきた有利に調子を合わせてきたのは、何と村田であった。何故だか、有利のサブの護衛であるグリエ・ヨザックまでいる。
「ど…どうしたの二人とも?」
「いやね?君に間男が登場したってある筋から噂を聞いたもんだから、気になってねぇ…はふふ、熱…っ…うまっ!」
村田はちゃっかり焼きたてのたこ焼きを買って、はふはふと頬張りながら好きなことを言っている。
「間男ってなんだよっ!…て、はふっ!」
そして、すかさず有利の口に入れてあげるのも忘れない。
「ふわぁ…何これ、凄い美味しいっ!こんなに美味しいたこ焼き初めてーっ!」
有利はたこ焼きのあまりの美味しさに、《家族の分も》と財布を開いたが、そこはさり気なく秋津に支払われてしまう。《お礼だから》と言われれば拒否も出来ない。
そんな有利達を見ながら、村田はもう一つたこ焼きを口に入れた。
「渋谷…ほら、僕って友達想いじゃない?」
そこまで自信満々に告知されると、《そうなの?》等とはなかなか聞きにくいものだ。
否定する要素も確かにないことだし。
「だからさ、君に変な虫がつくのは困るんだよね。で…直接見ておこうとこうしてわざわざ日曜日の夕方にやってきたわけだよ」
「狼の次は虫かぁ…。どっちも酷いなぁ」
秋津は苦笑しながらもさほど気にした様子はない。
なんとなく、鋭すぎる性格の人間をもやんわりといなしてしまう体質のようだ。
「それにしても美味しいねぇ。流石は名店《蛸大名》でトップ張ってる人だよね」
村田は小食気味のわりに、今日は随分と健啖なところを見せている。6個入りのたこ焼きはもう最後の一つとなっていた。
「えぇ…っ!?《蛸大名》って…あの、めちゃめちゃ行列が出来るとこ?」
その名は有利もテレビなどで見たり聞いたりしている。
確かに、今まで味わったことがないほど美味しいたこ焼きだとは思ったし、入っているタコが大きい割りに凄く柔らかくてジューシーなのも凄いと思ったが、何故そんな名店の人がこんな地方の公園で屋台などしているのだろうか?
「よぉ分かったねぇ…お客さん、たこ焼きマニア?」
「通って言って欲しいな」
ぷくっと頬を膨らませて村田が言えば、たこ焼き屋のおじさんは楽しそうな笑い声を上げた。
「秋津はんが《どうしても頼む!》なんて我が儘言うけぇ仕方なしに来てんけど…。名が知れちゃった店でのーて、屋台でこんだけ《旨い》言われたら、またおっちゃんも自信出てくるわー。みんなええ顔して食べてくれてやし」
「うん、だってめちゃめちゃ美味しいですっ!凄いなぁ…こんなにたこ焼き美味しく作れるなんて…!食べた人がみんな、幸せになるような味ですね?」
「おー、ええ顔して食べてんなぁ坊や。どや、もー一箱食べ?」
「良いんですか?やった…嬉しいっ!」
有利がはふはふとたこ焼きを頬張りながら全開の笑顔を見せると、おじさんはにこにこと笑み崩れ、コンラートは静かに表情を消し、秋津は嬉しそうに笑っていた。
そんな対照的な二人を見ながら、村田とヨザックは肩を竦めるのであった。
「どう思う?グリ江ちゃん」
「いや〜こう言うときに男の格って現れるって言うの?なんかー、隊長っでは余裕無さ過ぎみたいなー」
「うーん…困ったねぇ渋谷、友人としては《秋津氏に乗り換えてご覧》とか言いたくなっちゃうよ」
「ナニ勝手なこと言ってんだよ村田っ!」
友人達に駄目出しされているコンラートは、静かにたこ焼きを完食していた。
どれほど美味しいたこ焼きとはいえど、今の彼が味を感じられたとは思えなかった。
* * *
「秋津さん、たこ焼き美味しかったです!」
「ふふ…そりゃあ良かった。それじゃあこのまま、夜のドライブ…と言いたいところだけど、君は明日学校かな?」
「はい」
夕食が入らなくなるくらいたこ焼きを食べ尽くした後、有利は秋津にお礼を言うと帰り支度を始めた。
明日学校がなかったとしても、佐々野の運転する車に秋津・有利・コンラートで乗り込むというのは何やら胃が痛そうだ。
「また…会えるようにメール番号を教えてくれないか?」
「良いですよ。でも、その…俺、流石に二人きりで会うとかは出来ませんよ?」
「うーん…その約束はしかねるなぁ…」
困ったように小首を傾げる秋津に、コンラートの眦が釣り上がる。最近、かなり分かりやすく嫉妬を示すようになってきたのは気のせいだろうか?
「君は私と友達として付き合いたいのかな?」
「はい」
「うん、きっぱりして良い返事だねー。でも、私は恋人になりたいんだ。単刀直入に言うと、この美形護衛君との関係を友達付き合いに変更して、私と寝室を共にして欲しいんだよ」
「単刀直入すぎますよ社長…」
ドきっぱりとした秋津の物言いに佐々野はげんなりしたように肩を落とし、コンラートは…世にも恐ろしいほどの怨念を放出している。
「よくもまあ…いけしゃあしゃあと暴言を吐くものだな?」
「暴言じゃないさ。そりゃあ有利君は青少年だから、まともな大人である私はあと数年ほど我慢するつもりだけど…肉体関係を前提としたお付き合いをしたいってスタンスは明確にしておくよ?」
「あの…そういうのは、困ります…」
幾ら事情を知っている者ばかりとは言え(蛸大名のおじさんは屋台を引いて去っている)、健全な市民が集う公園のベンチに座って、一体有利達はどういう会話をしているのか…。
妙に迫力のある佇まいの集団に、道行く人々もちょっと興味を引かれたような視線を投げかけてくる。
* * *
「そう…困るかぁ。じゃあ、どうして君はそんなに美形護衛君が大好きなんだい?」
「え?」
「ストレートであることを殊更に主張して、君との関係を《気の誤り》みたいに言う男を、ずっと好きでいられる自信があるかい?…段々、辛くなってくるよ?」
常に飄々としいた秋津の表情が、その時だけは一瞬…沈痛なものを孕んでいた。
『そうさ…男同士なんて、ゲイであることの生態を認識している者同士でないとうまくいかない』
勝手に有利を《ゲイ》カテゴリーに含めている秋津は、苦いものが口内に絡むのを感じていた。有利達を見ていると、昔の記憶がどうしても蘇ってくるからだ。
「…秋津さん?」
「悪いことは言わない、私にしておきなさい。今の護衛君とでは…君は幸せにはなれない」
「どうして、辛くなるなんて言うんですか?そんなの…分からないじゃないですか」
「分かるさ…護衛君は確かに君のことを好きだろう。それこそ、頑固な生来の嗜好をねじ曲げざるを得ないくらい惚れ込んでいる…私に容赦ない嫉妬の睨みをきかせてくるくらいにはね。だけど、護衛君自身はそのことを恥じている。君を好きでいることが、護衛君にとっては苦痛を伴う事なんだよ」
「……っ!」
その言葉に、有利は口を封じられてしまった。
図星を指されたに違いない。
「随分と好き放題言ってくれるものだな」
しょんぼりと縮こまってしまった有利の姿に、コンラートの表情は先程までのそれが《柔和》と感じられるほど鋭利なものに変わっていた。
「そりゃあ言うさ。君みたいなのが我が物顔で有利君を独占してるんだと思うと、腹立たしくてしょうがないからね」
「それは、ご自分の経験則に基づくものですか?」
唐突に口を挟んできたのは村田だった。
意味深なその言い回しに、秋津は目元をすぅ…っと細めた。
「たこ焼き屋だけが君の情報カテゴリーではないようだね」
「広く浅くがモットーなものでね、秋津玲治…いえ、三松玲治…大手建設会社《ミマツ》の次男坊に纏わる噂も聞き及んでいますよ」
「まぁ…ね。姓は母方の秋津に戻っても、幾らかは三松姓の頃を覚えている連中もいると思ったけど…」
「社長、一介の高校生に何を言ってるんですか」
また佐々野が呆れたように窘めるが、今度は悪びれた風もなく秋津は硬い表情をしている。
「全く…有利君の関係者には驚かされてばかりだね。村田君って言ったっけ?君が唯の高校生の筈がない」
「え…?秋津さん、それってどういう…」
「渋谷、気にしないでよ」
「そうはいかない。私は有利君がどうしても欲しいんだ」
暗に、《不利になるような情報を流すようなら、こちらも容赦しない》と言いたげに秋津の瞳が細められる。彼は村田と顔を合わせるのは初めてなのだが、会話や表情の流れから巧みに情勢を見極めている。
村田にとっても、有利には知られたくない何かがあるのだ。
「ちなみに、あの事件のことは三松家と高岡家の連中が封じたがっていただけで、私自身にとっては苦くはあっても…消したいものではない。私を封じる切り札にはならないよ?そして…私は好きになった相手には秘密を持たない主義だ」
三松家と高岡家…秋津を拒絶した二つの家系は、巨額の金を使って醜聞を揉み消そうとした。何かの拍子に噂で耳に出来るような情報ではないのだ。
つまり…村田健という少年が、《一介の高校生》などではないことは明確だ。
「…ふぅん?」
村田からも、すぅ…っと表情が消えた。
「ねぇ、有利君…。聞いてくれる?積極的に教えたい話ではないけど…丁度君と護衛君にも当てはまるケースかな…っと思うしね」
「え…あ、ハイ…」
笑っているのに、目の奥に苦いものを滲ませた秋津に、有利は慌てたようにこく…っと頷いた。
→次へ
|