|
「君が欲しい」−3
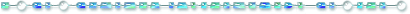
秋津玲治は昔話をした。
彼がまだ三松姓を名乗っていた大学生の頃、既にゲイであることを自覚していた彼は初めて激しい恋をした。
相手は幼馴染みで、同じ大学の職員として勤務していた高岡修史だった。
高岡家は代々政治畑の家柄だったせいか、線が細く大学の研究室から出てこない修史は家族の理解を得られぬ孤独な存在であったらしい。
また、容貌が整いすぎて冷ややかな印象のあった高岡は、能力的には問題ないのに、コミュニケーション能力の低さによって研究生に甘んじているような男だった。
ただ、同じ研究室に所属するようになってから、玲治の紹介で人との繋がりを得て助教授に昇格することになった。
玲治が身を惜しまず彼のために尽くしたのは、昔から憧れの対象であった彼を全ての意味で手に入れたかったからだ。
修史もまた、熱烈なアプローチを受ける内に身も心も開いて《恋人》であることを容認してくれるようになった。
玲治は美しい恋人に夢中になった。
自分の持てる全ての力を尽くして、修史を幸せにしようと努めた。
だが…ある日、玲治には思いがけないような形で二人の関係には終止符が打たれた。
元々はごく普通の性嗜好を持っていた修史にとって、友達の繋がりが豊かな玲治はあまりにも《尻軽》な恋人に感じられたらしい。男である修史を好きになったのだから、男であれば誰とでも関係を結ぶとでも思っていたのだろうか?
恋人として愛しているのは修史だけだと何度説明しても、男女を問わず気に入った相手とは友人関係を繋ぐ玲治に、修史は強い嫉妬を感じ続け…ある日、壊れてしまったのだ。
『殺してやる…っ!この…浮気者…っ!』
綺麗な顔を憔悴に歪め、修史がナイフを持って襲いかかってきた日のことを…玲治は生涯忘れないだろう。
愛していたのに…誰よりも愛していた人の刃を、胸に突き立てられた。
一緒にいた後輩は別に玲治に恋愛感情なんてものは持っていなかったし、玲治もまたそうだった。だが、修史にとっては小綺麗な少年と共にいるだけで、耐え難い裏切りのように感じられたらしい。
幸いナイフの刃先は急所を逸れたので、玲治は後輩に口止めをした上で修史を自宅に戻し、そのまま自力で病院に行った。
この事件について玲治の側に訴える気など毛頭無かったのだが、互いの家は激しく反応した。
三松家では凶器を持って襲いかかってきた修史を責め、高岡家ではそんな心理状態に追い込んだ玲治の性癖を責め立てた。
だが、互いにとってそれが表沙汰になることが企業ダメージに繋がると理解した途端、今度は二人の息子達を封じに掛かった。
『何もかも、無かったことにしろ』
そう言われ、修史から引き離されたのだ。
今でも玲治は修史がどうしているのか知らない。
優秀な佐々野に一言命じれば調べてくれるのかも知れないが…あるいは、知ることが今となっては怖いのかも知れない。
お互い愛し合っていたはずなのに、最悪の形で関係を崩壊させてしまったことが鈍い刃のように刺さったまま、胸を苦しくさせるのだ。
* * *
「…というのが、我が三松家最大の醜聞、《ゲイ次男刀傷事件》だよ」
「そんな…」
皮肉げに唇の端を上げ、秋津は語り終えた。
話をしていく内にどんどん蒼白になっていく有利の表情から、《ああ、これは引いたな…》と感じたのは確かだったが、今更どうしようもない。
村田にほのめかされた段階で、有利に近づけば必ず明かされてしまうことは必至だったから、第三者の口から漏れるくらいなら自分から伝えたかったのだ。
人からどう言われようとも、それが秋津の生き方だった。
「そんなわけで、私は初めて愛した人を不幸にしてしまった甲斐性無しだ。そんな私が君を幸せに出来るとは言い切れないが、少なくとも…護衛君よりは相性は良いはずだよ。私は、《恋人と友人は別のもの》だということを感覚的に分けて扱えるからね」
それが出来なかったからこそ修史は破滅し、コンラートもまた有利に必要以上の嫉妬を感じているのだ。それが段々とエスカレートしてくれば、コンラートの方が遙かに膂力に優れ、特殊な方法も知るだけに…監禁や度を超したお仕置きといった不幸を招きかねない。
見ず知らずの秋津に真心からタイ焼きを奢ってくれるような有利を、そんな目に合わせたくはなかった。
秋津を選ばないのだとしても、コンラートとだけは距離を置いて欲しいと思うのだ。
だが…有利の反応は秋津の予測から大幅に逸脱するものだった。
「好きだった人と、そんな形で引き離されるなんて…酷い…っ!」
「……は?」
「秋津さん、絶対高岡さんの居場所を突き止めようよ!そんで…別れるにしてもやり直すにしても、もう一度会ってちゃんと話をしなくちゃ!」
「あー…いやいや、有利君。あのね?あれから二十年近くたって…」
「どんなに時間が経ったって、好きな人を《不幸にした》って思ったまんまなのは絶対駄目だよ!」
「……!」
それは、あまりにも青少年らしい真っ直ぐな主張で…秋津は有利を眩しく感じると同時に、少し怯えてしまう。
「せめて、今どうしているのか調べられない?ねぇ…村田…。色んな情報集めるの得意なんだろ?知らない?高岡さんがどうしているのか…」
「……知ってるよ。高岡家の本家がある山口県の山奥で、座敷牢に閉じこめられてる」
「えーーーっっ!?」
ショッキングな内容に、有利と秋津の声が同時に上がる。
「座敷牢だって…!?今…何世紀だと思ってるんだっ!大体、二十年も前の事件だぞ?」
秋津もそんな事態までは想像していなかった。元々高岡家の中では変人扱いされていた修史だから、さぞかし強い風当たりを受けているだろうとは予測していたのだが…まさか、そんな扱いを受けているとは思わなかった。
怒りと憤りに唇が戦慄いてしまうことで、ふ…っと気付くこともある。
『二十年…これだけ経っても、私は修史を忘れていないのか?』
忘れていないどころか…疼くように込み上げてくるこの想いは、やはり一つの形を為すのだ。
彼に対して…まだ何らかの感情を強く持っているのだと。
「タイミングを逸したって事だろうね。家族もそこまで彼を罰しようという気持ちはもう無いんだろうが、高岡さん自身も基本的に引き籠もり気質だから、座敷牢の中に研究設備だけは整えて貰って静かに暮らしてるらしいよ」
「は、早く出してあげなきゃ…っ!」
逸る有利を窘めるように、村田は緩やかに首を振った。
「待って、渋谷。二十年…監禁というよりは軟禁にされていただけなんだ。高岡さんは、出ようと思えば出られた筈なんだよ。それでも彼が座敷牢の中に籠もっていたのは、彼自身がそれを望んでいたというのもあるんじゃないかな?新たな刺激を与えられて…それも、殺したいくらいに愛していた男が伸び伸びと社会活動を営んで、男子高校生に愛の告白までしてるなんて知ることは、拷問級の酷いことなのかも知れないよ?」
「でも…高岡さんは、絶対後悔してると思うんだ。好きな人を、傷つけちゃったんだよ?少なくとも、秋津さんがナイフで刺されてもやっぱり好きだったって事だけは伝えてあげなきゃ…っ!」
「ユーリ…それはあなたの感じることで、タカオカの感じ方とは違うでしょう?蒸し返すことは、彼に死を選ばせかねない」
「……っ!でも…っ」
コンラートの言葉に、有利は幾ばくかの躊躇を覚えたものの…それでも思いの丈を言の葉に乗せた。
「違うかも知れない…だけど、間違いを起こすような恋だったから、《無かったことにする》なんて俺は嫌だ…っ!本当に無かったことに出来てるなら良いけど、秋津さんは今も苦しんでるじゃないか…そうだろ!?」
コンラートと秋津は何かに打たれたように背筋を伸ばした。
幼い気質の少年が見せる鮮やかな主張は、時として世慣れてしまった男達を強く刺激するものらしい。
「だって、好きだって気持ちはどうにもなんないもん。やれることを精一杯やってもないうちに、諦めたりなんかして欲しくない!」
「……俺が、タカオカと同じようにあなたを刺す日が来ても…同じ事を言えますか?」
「言えるよ!だって、どんなことされても…俺はあんたが好きだもんっ!」
有利は勢いが付いてしまったのか、頬を上気させたまま秋津に向き直った。
「俺を心配して、助言してくれてありがとう。でも…俺、やっぱりコンラッドが好きです。嫉妬されて酷いお仕置きを受けるようなことがあっても、《これは止めて》ってちゃんと言った上でコンラッドと付き合っていきたいんです。それが不幸か幸せかは俺が決めるから…心配しないで下さい」
「………こりゃあ…一本取られたね」
秋津は何とも言えない顔をして頭を掻くと、深みのある微笑みを湛えて有利を見つめた。
「君は…大した子だよ。本当に興味深い」
「いやいや…俺、普通の高校生だし。買いかぶりすぎです」
「そんなことないよ。私に、昔の恋の始末を付ける気にさせるくらいだもの…」
「じゃあ…」
有利の瞳が輝く。
《こうすべき》という思考展開にかけては、有利と秋津はやはり近いものがあるのだと思う。
例え相手に共感できない部分があっても、否応なしに愛さずにはいられない感覚は秋津も知ることだった。
《都合が良い》からといって簡単に乗り換えられない…それは、尤もな話であった。
そんなに打算的な付き合いが出来る子なら、はじめから有利に惹かれたりはしていないと思う。
「ん…。君のことを好きだなんて知った時に、修史がまだナイフを取りたくなるくらい私のことを好きかどうかは分からないけどねぇ…。少なくとも、私は彼を恨んだりはしてないって…伝えてくるよ」
「そのまま二度と帰ってこないでくれるとありがたいな」
コンラートの突っ込みはいっそ清々しいほどに鋭利であったが、秋津もしぶとい性質であった。
「い・や・だ。自分でも吃驚するくらい修史の話をぶり返されて、昔の感情も蘇ったがね?私は益々有利君のことを気に入ってしまったんだ。全てケリをつけてまた戻ってくるさ。たとえ君に古傷を刺されようともね」
「では、勝手に帰ってくるが良い」
そう言うと、コンラートは男の沽券も羞恥心も何もかも蹴り飛ばすような勢いで有利を抱きしめた。
「お前が来ようが誰が来ようが…決してユーリは渡さない。ユーリは、俺のものだ」
「あーあ…こんな子どもっぽい独占欲で凝り固まった男、まだ好きだって言うのかい?有利君…」
呆れたように唇を尖らせる秋津に、有利は困ったように苦笑するのだった。
「すみません、こういうところも全部ひっくるめて……スキです」
「ふふ…しょうがないなあ…。どうして恋って、会社経営みたいに上手くいかないんだろうね?」
この不景気に世の経営者が聞けば《巫山戯るな》と言われそうな言葉を発しながら、秋津は佐々野に車を回すよう命じた。
上司の深い事情を知ることとなった佐々野は、少ししんみりとした顔をしてその場を後にした。
* * *
「やれやれ…渋谷ってば本当に、濃い人に好かれやすいよねぇ…」
「…ってことは、お前もかよ村田」
「さてねー…」
ホテルに戻ってきた有利達は夕食は流石に入らなくて、軽食を摘みながらカフェインの入っていない飲み物を口にしている。
「そういえば、村田って凄い情報網持ってんだなぁ…ああいうのって、何処でどうやって知るの?」
「グリ江ちゃんとお友達になれたからだよ」
「そっかあ…そういえば、昔からの友達みたいだもんな」
その言葉に、ぴくりと村田とヨザックが反応する。
「…渋谷、昔からって…?」
「え?だって俺の護衛さんとして雇われてからの付き合いだったら、あんなに砕けた物言いとか意味深な会話とかしないだろ?」
「はは…まぁ、ねぇ…」
曖昧に頷きながら、内心ひやりとしたものが村田の背筋を伝う。
正直…秋津と対決モードに入ったときにも何かを暴露されるのではないかと警戒していたのだが、あの程度のほのめかしで済んでほっとしていたのだ。
それが、まさか有利自身の気づきで以前から感ずかれていたとは思わなかった。
「あのさ…渋谷は、僕が君に何かを秘密にしていたりしたら…嫌?」
「村田が言いたくないことだったら良いよ」
そうやって、有利はさらりと笑って包み込んでくれるのだ。
傷つきたくなくてこうして今日も黙ってしまう村田は、同時に何もかも彼にさらけ出した上で、汚れた傷を塞いで欲しいとも願ってしまう。
『…狡いよね』
分かっていても、こうして縋ってしまう村田を…いや、村田達を…いつまで有利は許してくれるのだろうか。
「君ってさ…そんなに何でもかんでも許してたら、そのうち酷い目に遭うかも知れないよ?」
「酷いのはやだなぁ…」
本気でそう言って、不安げにお茶を啜るから…村田はツキンと胸を突かれてしまう。
秋津玲治…自分の印象に不利になると分かっていて、ほのめかされた過去を有利に明示して見せた男は、有利の眷属とも言える性質の持ち主であったのかも知れない。
村田は、同じだけの強さを持って有利に真実を告げることが出来るだろうか?
喉奥にこみあげてくるものを感じながら…それを今日もお茶で流してしまうのだった。
* * *
慌ただしい一日が過ぎ、お風呂に入った後の有利をコンラートの腕が包み込んだ。
珍しく懐いた猫みたいにまふまふとした毛触りのローブへと擦り寄ってくるから、有利は不思議そうに顔を仰け反らせた。
「どうしたの?」
「日中、やられっぱなしだったので悔しいんです」
「やられっぱなし…?」
有利はきょとんとしたように小首を捻る。
コンラートは鋭く秋津を攻撃していたくらいで、やられているようには感じなかったのだが…。
「コンラッド…秋津さんに言い負かされたりしてなかったじゃん。ちゃんとやり返してたよね?」
「…子どもっぽい抗弁でね」
ふぅ…っと吐かれた溜息は苦々しいものだった。
「正直…タカオカの話は堪えましたよ。嫉妬が高じて…あなたを傷つけるなんて、耐えられない」
「コンラッド…」
ぎゅ…っと強く引き寄せられて少し苦しかったけれど、有利の胸には暖かいものが込み上げてくる。
コンラートは原則として意固地な性格をしているくせに、時折こうして吃驚するくらい素直になるのだ。
「あなたは傷つけられても俺を赦すと言ったが、俺は赦せない…。多分、アキツもタカオカを恨んだりはしていないでしょうが、タカオカが今…隠居生活とはいえ生きているのが不思議なくらいだ」
《俺なら…》の後に続く言葉が怖くて、有利は無理矢理身体を捻るとコンラートの唇を自分のそれで塞いでしまった。
「…口封じがお上手になられた」
「あんたのおかげでね?」
口を開いた途端に、押しつけるだけだった不器用なキスが、舌を絡め合う濃厚なものへと変化する。
「ん…」
「あなたが…俺だけにしか興味がない人だったら良かったのに」
「そんなつまんない奴なら、とっととあんたは見限りそうだ」
「見限ったりしませんよ」
ソファに横たえられ、タオル地の柔らかいローブをはだけられて肌を晒されると、コンラートは悩ましい吐息を吹きかけながら…熱く囁いた。
「愛してます…どんなに俺の思い通りにならなくても」
「いつもそんなに分かりやすく教えてくれたらいいのに…」
剛速球で良いから、いつも直球を投げて欲しいものだ。
ビーンボール紛いのカーブを投げられても好きでいる自信はあるが…身体は保たないかも知れないから。
「素直すぎる俺なんて…それこそ、つまらないんじゃないですか?」
「つまんなくなんか、ないよ。今…凄い嬉しいもん」
「…全く。あなたには敵わない」
くすりと微笑むコンラートの口元が、日中浮かべていたような冷たい形ではなく、少し嬉しそうに綻んでいたのが印象的だった。
「こうしてまた、俺はあなたに溺れていくわけだ…。アキツにも指摘されましたが、確かに俺はあなたという蜜に熔かされてしまうことを恐れています。どんどん、自分が自分でなくなっていくような…そんな恐れです」
「う…、でも…頼むから《無かったこと》にはしないで?」
「出来るようなら、とっくにやってますよ」
するりとローブの合わせ目から潜り込む指に翻弄されながら、有利は明日の授業のことを考えないようにした。
滅多にないコンラートの素直な態度を、スポンジのように精一杯吸い尽くしたいのだ。
冷たくて暖かくて、捻くれていて真っ直ぐで…そして堪らなく愛おしい人。
何があってもこの人を手放したくないのは、有利も一緒なのだ。
「大好き…」
思いの丈を込めて囁けば、語尾が思わず弾んでしまう。コンラートを好きでいることがこんなにも嬉しいのだと、少ない語彙ながら伝わったろうか?
「堪らないな…あなたを知るたびに、触れるたびに…抵抗しても否応なしにあなたに惹かれてしまう。もう…抗うことを止めてしまいたいくらいに」
どうやら、効果はあったらしい。
コンラートはクリティカルヒットを受けたらしく悶絶し、淡く上気した頬を手の甲で擦っていた。
伏せられた睫は長くて、頬に落ちた影へと唇を寄せてしまう。
《可愛い》…なんて、思ってしまったのだ。
「そうしてくれたら凄く嬉しいんだけどな」
「そうしてあげられたら俺も楽なんですけどね…」
互いの唇には同じ形状の笑みが浮かんでいた。
分かっていても止められないのは、お互い様な部分があるからだ。
「不器用で、すみません…」
「ん…」
不器用極まりない恋人は、対照的に器用な舌遣いで易々と有利の感覚を煽っていった。
* * *
数週間の後、秋津から連絡が入った。
《夕食を共にして欲しい》とのお誘いに、当然のように複数の参加者が出た。
「いや〜…皆さんお揃いで……」
デートといういうより定例の飲み会のような雰囲気になってしまっているが、一応会場は《ラ・ティール・トゥール》という有名な鴨料理専門店で、普通はこのように飛び込みの客が入る余地など無い。
だが、秋津は最初から分かっていたかのように面子分の予約を取っていてくれた。
有利が初めて食べる鴨肉の芳醇さにうっとりしていると、秋津は淡々と《昔の恋の後始末》について語ってくれた。
「修史は、意外と元気にしてたよ」
そこで何があったのか秋津は詳細を語ることはなかったし、有利もまた聞いたりはしなかった。
手を尽くして、そこで何が起こるかまではどうにもならないと分かっているからだ。
ただ、少なくとも秋津の表情には一定の満足感があったことが、有利を安堵させていた。
『きっと、秋津さんなら大丈夫』
まむまむと紅いソースに絡めた鴨肉のソテーを咀嚼していると、秋津は穏やかな眼差しで有利を見やった。
「…君は、やっぱり護衛君を選ぶのかい?」
「はい」
「良い返事だなぁ…ああ、やっぱり君が好きで堪らないよ」
「好きでいてくれるのは構いませんけど、それって恋とかそういうんじゃないと思いますよ?」
「おや…そう思うかい?」
不本意そうに眉根を寄せていた秋津だったが、有利がこっくりと頷くと…諦めたように肩を竦めた。
「君って子は、本当に不思議だね…鈍いように見えるのに、時々とても鋭く真実を指し示す。だからこそ多くの者を魅了するのかも知れないね」
「さあ?」
《魅了》云々は分からないけれど、それでも…秋津の想いが口にしているような《恋情》を孕んだものでないことは確かだと思う。
「年を取って、私も人生の上手な渡り方を覚えたと思ったんだけどねぇ…。やっぱり私は修史を忘れられていないんだと思うかい?」
「秋津さんが一番よく分かってると思いますよ」
「そうだね…」
秋津は微笑むと、後は静かに食事を続けた。
その様子は、鴨肉よりも自分自身の思いを噛みしめているかのようだった。
それでも食事を終えて別れの間際に見せた表情は、穏やかな中にも何かを定めているように見えた。
「有利君、私はまた修史を不安にさせてしまうかも知れない。それこそ、今度こそとどめを刺されかねないくらいにね。けど…それでもやっぱり、修史以外の男にも女にも、興味を持ったら話し掛けに行くと思うんだよ。君みたいな子に会えるのは、人生の得がたい喜びだからね」
「俺も、秋津さんに会えて良かったですよ」
「ありがとう…何よりの言葉だ」
秋津はぽふりと有利の頭に手を載せると愛おしげに撫でつけてくれたが、コンラートは不機嫌そうな顔をしつつも止めようとはしなかった。
「おやおや…護衛君は《ウェイト》を覚えたのかい?」
「犬扱いは不本意ですが…とりあえずあなたがユーリを傷つける恐れはないと知っていますから、止めません」
「ふふ…大した成長だ。やっぱり若いって良いねぇ…」
「社長、オッサンくさいです」
佐々野がすかさず突っ込んでくる。
彼は別にゲイではないそうだが、秋津とは何とも良い間合いの芸人のような関係だ。
「いやいや、本当にねぇ…しみじみ感じるよ?若いときに、何でもーちょっと頑張っとかなかったのかってねー…」
彼には珍しい後悔の色は、やはり高岡修史とのことを差しているのだろう。
もっと早く本気になって彼を捜していたら、別の関係を築けたのではないかと…。
「有利君、私がまた刺されたら慰めてくれるかい?」
《まず刺されないようにして下さいよ》と言いたいが、同じ病癖(?)を持つ有利が言うことでもないだろう。
「はい。コンラッドとお見舞いに行きます」
「ははは…楽しみにしているよ」
「社長、まず刺されないで下さい」
佐々野が遠慮無く突っ込みを入れてくる。
本当に良いコンビだ。
「あなたみたいな人でも、いないと会社は本気で困りますから」
「《あなたみたいな人でも》って佐々野…言葉が厳しいよ佐々野…」
「では…」
佐々野は眼鏡の蔓を中指で押し上げると、綺麗な笑みを見せた。
「私が本気で困りますから、刺されたりしないで下さい」
「うん、それなら気を付けよう」
こっくらと頷く秋津は気付いているだろうか?佐々野の送る眼差しが、一瞬…切ないような色を滲ませたことに。
二人が立ち去った後、村田もぽんっと有利の肩を叩いてきた。
「彼も意外と天然入ってるのかな?あの美人の秘書さん、ストレートだって言い張ってたけど…社長に惚れかけちゃってんじゃないの?」
「わー…どうなるんだろうね?」
「全く…辺り構わず魅力を振りまく人が回りにいると、色々と苦労するものですね」
素朴な好奇心にわくわくしていたら、コンラートに溜息をつかれてしまった。
「それってどういう意味?」
「聞いたままですよ」
鼻で笑ういつもの表情を見せるけれど、コンラートの手は優しく有利の背を促した。
「さあ…帰りましょう」
「うん」
有利達の住むあの部屋に帰ろう。
起こってもいないことを恐れて怯えることがあっても、あの部屋の暖かさは…きっとそんなものを乗り越えていけるだけの力をくれるから。
大切な人を、信じる力を…。
おしまい
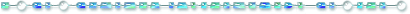
あとがき
話を要約すると、「タイ焼き食べてたこ焼き食べて鴨食って、次男がちょっぴり素直になる話」でした。
わーん、また今回も何の事件も起こらずに終わってしまいました!
ハードボイルド系のお話はほとほと合っていないのか…。
次男が父ちゃんの死のトラウマを乗り越えたり抵抗なく有利に溺れたり、村田の正体が明かされる日は来るのでしょうか!?
ただ、次男に関してはそれが成就された場合《クールビューティー閉店》になりそうなので、そこでシリーズ完結でしょうね。ちょっと昔の美容院が時流に負けて閉店しているような響きですが…。
いつか良い感じの事件を思いついたら完結させたいものです。
秋津さんは結局、「有利を大好きだけど恋愛感情とはちょっと違う」という感じになっちゃいました。狂おしいほどに有利だけが好きな人にした方が良かったのかもしれないのですが、そうするとオチをどう設定すれば良いのか分からずあのようなことになりました〜。
まあ、なんやかやで幸せになりそうな人です。
人間性勝負になると次男はとっても不利になってしまうので(クールビューティーの筈が、単に大人げない人にしてしまっているので…)、次回は活劇が入るとイイナと思っております。半年に一回くらいのペースで更新されるこのシリーズ、まだ暫くお付き合い頂ければ幸いです。
|