|
「君が欲しい」−1
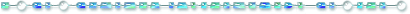
見上げると、視界いっぱいに薄青い空と鱗雲が広がっている。
橋の真ん中だから余計に視界は広々としていて、吸い込まれそうに感じた。
腕を広げて深呼吸をすれば、冷たいけれど澄んだ空気が胸一杯に広がる。
『あ〜…開放感!』
とはいえ、実のところ渋谷有利の身は始終監視の視線を浴びてはいる。ただ、護衛…コンラート・ウェラーは時折こうして距離を置いてくれるので、ちょっぴりの寂しさと共にひとときの開放感を味わったりする。
本日は十月最後の日曜日であり、友人の村田と草野球チームの備品などを買い出しに行ったので、その間は遠目に見守ってくれているのだ。
村田とは橋のあちら側で別れたから、そろそろ寄り添いに来てくれるはずなのだが…。少しの間、完全な一人(みたいな)時間も取ってくれているのだろうか?
『こういうとこ、細やかなんだよなぁ…』
護衛はあまり口数が多くないので、どういう心情でこういうことをやっているのかはよく分からない。
《優しさ》だと感じるのは、ひょっとしたらそう思いたい有利の心情が反映されているのかも知れないが…確認する術はない。
『…なんせ、謎が多いんだよね』
いや、実のところ本当に謎なのは有利の身の上の方かも知れない。
有利がごく平凡な男子高校生だったのは一年生の夏までで、今では世界有数の大金持ちとなり、財産狙いの悪漢にいつ襲われるか分からない状況になっている。
血の繋がりがあるわけでもないのに、巨大財閥の総帥である権現氏が、莫大な遺産を有利に贈与してくれたからだ。
色々あって、財産の使い道としてNPO法人の幾つかに支援を行うようになったのだが、それでもなかなか財産はなくなりはしなかった。
正直、有利としては持て余しているのだが…何かを期待して贈与してくれた権現氏のために、何が出来るのか模索中という段階である。
権現氏は有利が巨大な遺産を受け継ぐことで、生活に混乱を来したり、その身が危うくなることがないよう十分考慮してくれた。遺産管理に携わる専門の弁護士甲田と、有利の身を直接護るコンラートを派遣してくれたのだ。
『ほんっと、俺って恵まれてるよな…』
本当に感謝しているのだが、直接巨額の金を目にすることはないため、有利としてはまだ自分が大金持ちであるという自覚がない。財布の中に一万円以上の金額があると落ち着かないので、基本的に現金もカードも持っていないのだ。
今も財布にはじゃり銭が何枚か入っているだけなので、下手すると小学生よりも持ってない。
防衛システム完備の自宅が完成するまでは…と、豪華な一流ホテルのスウィートに住んでいるのだが、今でもホテルに入る時に学ラン姿の自分に引け目を感じてしまうくらいだ。
『なかなか、慣れるもんじゃないよね』
また、簡単に慣れてもいけないのだと思う。
溢れるような贅沢を当然と思うような有利に、権現氏は財産を残したかったわけではないだろう。
ぴゅう…っ
木枯らしが吹き抜けていくと、晴れている割に気温が低いせいで身が縮こまりそうになる。そろそろ以前の自宅押入に入っているベストか、薄手のマフラーを引きずり出した方が良いかも知れない。
でも、取りあえず当座は温かいものでも口にしようかと思い、橋を越えたところにある公園に入っていった。ここは結構規模の大きな公園で、週末には幾つかの屋台が立っていたりする。
今日もタイ焼き屋が出ているようだ。
『本当はたこ焼きが良かったんだけどな…』
確か、コンラートはまだタコ焼きを食べたことはないはずだ。タイ焼きも無いかも知れないが…勝手な印象としては、甘いものより辛いものの方が好きな気がする。
買って待っていたら、丁度食べ頃の時に寄ってきてくれるのではと期待していたのだが…。
『タイ焼きだったら来てくれないかな?』
まあ良い。ひょっとしたら、カリカリした端っこの部分は喜んでくれるかも知れない。あの部分なら少しくらいさめても美味しいだろう。
相当庶民的な事を考えながら屋台に寄っていくと、随分と場違いな男性がタイ焼き屋のおじさんと揉めていた。
「カードでは買えないのかい?」
「無茶言うなよ兄ちゃん。見りゃ分かるだろ?」
「すまない…初めてこういうところで買うものだから」
財布から取り出していたカードの種別にぎょっとする。
先日、コンラートに教えて貰ったばかりの《ブラックカード》は、戦車も買えるという代物だ。
『お忍びで来たお金持ちの人なのかな?』
有利とは別の意味で、異文化コミュニケーションに頓挫しているのかと思うとちょっと微笑ましい。
「お兄さん、赤あん・白あん・カスタードのどれが良い?」
「え…?」
「折角だから、奢ったげるよ」
断りの隙も与えずに、青年の視線が送られていた赤あんを三つ注文する。
「赤あん三つね。二つは同じ袋にしても良いかい?」
「ううん、袋はいらないから手で持てるように紙を三枚つけてくれる?」
「はいよ」
計算通り、じゃり銭は綺麗さっぱりなくなった。
お財布は見事にすっからかんである。
「はい、どうぞ」
「すまない…。私はこういう者なんだが、後で礼をさせて貰えるかな?」
タイ焼きと交換に、名刺を差し出す動きはとても綺麗な所作で、何となくコンラートを想起させた。彼は護衛などという無骨な職業の割に、やはりソフィスティケートされた男なのだ。長期の任務だと雇い主と共にパーティーにも出かけたというから、そういうところで身に付いたのだろうか?
「あー…ごめんなさい。俺は名刺とか持ってないんだけど…」
「はは。高校生が持ってたら驚くよ」
「確かに!」
思わず、くすくすと笑い合う。
有利が言うのもおかしいが、お金持ちっぽい人の割に屈託のない人だ。
名刺で名前を確認すると、《秋津玲治》という名前で、肩書きはなんだかまた立派そうだ。どこかの企業の代表取締役だそうだが、具体的にはどういう仕事なのかよく分からないので実感はわかない。
『二十代後半から、三十代前半ってとこかな?』
何でもかんでも引き合いに出して悪いが、コンラートと同じくらいか、少し上に見える。
仕立ての良いスーツの上に薄手のコートを纏い、良く磨かれたエナメルの靴を履いている。不用意に座ったりしたら汚れが気になりそうだ…と思ったのだが、彼は気にすることなく有利を誘って公園のベンチに座った。
「ん…美味しい!」
「うん、これはなかなか。端っこがカリカリ〜」
はふはふと囓れば、熱くて美味しい餡とカリッとした皮が口の中で楽しいハーモニーを奏でる。
「コンラッド、まだ来ないのかなぁ…」
タイ焼きを半ばまで囓ったところで、もう一尾をたべてくれる筈の人が気になってきた。
「そっちのタイ焼きは友達用?」
「うーん、友達っていうか…」
《護衛です》とは言いにくいし、《恋人です》はもっと言いにくい…。
『恋人…』
その言葉を口の中で反芻すると、何だか頬が熱くなる。
有利から迫る形で押し切ったので文句を言う筋合いはないのだが、この恋人は結構な自信家で天然で無自覚Sなので、時折恥ずかしくて死にそうなセックスを仕掛けてくることがある。
昨日の夜なども《明日、村田と二人で買い物に行きたいんだ》と言ったら、平然として《そうですか》と言っていたくせに、床の中では意地悪の限りを尽くされた。
いや…意地悪というか何というか…本人はやはり自覚していないのだろう。彼は意外と嫉妬深くて、自分以外の誰かと有利が近寄りすぎると、有利の愛情を試すようなことをしてくれるのだ。
昨夜も、何度も叫ばされた。
『大好き…コンラッド…っ!』
『あ…あんただけを、誰より大好きだよ…っ!』
喉が嗄れるまで叫ばされるのは、乾燥とウイルス感染が気になるこの季節には如何なものかと思う。
「どうかしたの?」
「ううん、何でもない」
ふるる…っと首を振って、残りのタイ焼きを乱暴に口の中へと突っ込んでいたら、やっとコンラートが公園の木々の間から姿を見せた。嬉しくてぴょこんとベンチから立ち上がったのだが、危うくそのまま逃走を図りそうになった。
なんだか…コンラートの背後におどろおどろしい気配が漂っているように見えるのは気のせいだろうか?
その様子に、はっと有利は気が付いた。
公園のベンチに見知らぬ男性と座っているなんて…コンラートに《虐めてください》と言っているようなものではないだろうか?
それに、護衛の立場としても《知らない者に、安易について行かないでください》という注意に背いている。言われた時には《子ども扱いすんなよ》と笑っていなしたのだが、この状況は何とも説明に困る。
『ど…どうしよう〜っ!』
おろおろと立ちつくしている有利に、秋津が不思議そうな眼差しを送ってきた。
「どうかしたの?」
「あ…あの…。《知らない人と一緒にいたらいけない》って、あの人に怒られるところなのかな〜と」
「それはまた…えらく過保護なことだね」
「いや全く…」
逃げるわけにも行かず(そんな事をしたら倍にして意地悪される)、有利は近寄ってきたコンラートに引きつった笑みを浮かべた。
「コンラッド、タイ焼き食べる?」
「結構。甘いものは苦手ですので」
案の定、予想通りの言葉が返ってくる。
「ふぅん…気の毒にな。こんなに美味しいに」
秋津は最後の尻尾部分を名残惜しそうに味わうと、有利に向かって微笑みかけた。漆黒の艶やかな髪を後ろに撫でつけた秋津は、やさしげに笑うと目元に人好きのする皺が浮かぶ。たくさん良い笑いをしてきた人の顔だ。
「良かったら、そのタイ焼きも貰って良いかな?」
「うん…コンラッドが食べないなら……」
しょんぼりしてタイ焼きを渡すと、秋津は責めるような視線をコンラートに送った。
その一瞥には、先ほどの笑顔とは違う…男の凄みのようなものが漂っていて、コンラートのナイフのように鋭利な表情と相対すると、間に氷雪の烈気が漂う。
「タイ焼き二尾のお礼…必ずさせて貰うよ」
「良いよ。美味しく食べて貰ったら、タイ焼きも本望だと思うし」
「私が、君にしたいんだ」
人を逸らさぬ笑顔で押しだし満点の申し出をされてしまった。
この若さで企業の役員をやっているだけあって、一度こうと決めたら何が何でも押し通す人なのかも知れない。
「来週もここで、この時間に会えるかい?」
「え…?」
有利は慌ててコンラートを見上げた。
コンラートは最初の不機嫌な表情を端正な仮面の下に押し込んだらしく、綺麗に微笑んで有利を促した。
「構いませんよ、ユーリ。アキツ氏は身元の確かな方です。不審な行動をみせるようならすぐに対処できます」
「身元が確かときたね…」
秋津の方はコンラートの言い回しがいたく気にくわなかったらしく、あからさまに《カチンときました》という表情をみせたが、こちらもすぐ営業用の笑顔に切り替えてきた。
「君はこの子の恋人?だったら、私にも可能性があるかな」
「仰る意味が分かりませんが?」
冷たくコンラートが言い捨てると、秋津は男らしくがっしりとした顎を指先でなぞりながら、響きのよい低音で恐ろしいことを言いだした。
「私はストレートの子に無理強いするのは好みではないので、君が顔を出してくるまでは自粛しようと思ってたんだが…。どうやら、ユーリ君は不本意ながら君の身体を知っているようだ。素養はあると見て良いのかな?」
「不本意…ね。誘ったのはユーリの方だが?」
《頼み込んでさせて頂いたというわけではない》…そう言いたげなコンラートの言葉に、有利の頬が真っ赤に染まる。
そんな有利を、秋津は大人の余裕たっぷりの声で慰めてくれた。
「はは…大人げないな。確かにそのようだけど…男の真価はそこからの扱いだよ?ねえ、ユーリ君。私に乗り換えろ…とは言わないから、ちょっと味見をしてみないかい?その年で青臭い男一人しか知らずに終るには、君は魅力的過ぎる。勿体ないよ」
「あ…秋津さん、何言ってんの!?」
いや、秋津だけでなくコンラートもコンラートだ。
確かに有利が彼を欲したのは事実だが、知らない男の前で身体の関係があることを認めなくたって良いではないか。
何やら鼻の奥がつぅんと痛くなって、目元が熱くなってくる。
でも、こんな好き放題言い合っている男達の前でみっともない所なんか見せたくなくて、有利はギロリと二人を睨み付けると、ぷん…っとそっぽを向いて早足に駆けだした。
「もー知らないっ!あんたら、勝手にいい男自慢でも何でもしてろよっ!」
「ユーリ!」
しかし、二人とも簡単には行かせてはくれなかった。
護衛として世界的に名を知られているコンラートだけでなく、秋津の方も身体は十分に鍛えているのか、すぐに両脇から挟み込むようにして有利を捕らえてしまったのである。
二人が群を抜く長身であるだけに、まるで捕獲された宇宙人のような有様になる。
「すまない…ユーリ君。君の意志を無視するようなことを言って…」
「離してくれよっ!どうせ俺なんて、年上の美形の外人さんに身の程知らずに惚れて、逆上せあがって…勝手にくるくる回って、勝手に期待して…勝手に傷ついて凹んでるだけなんだからっ!」
力ずくで止められたのが悔しくて、二人の男に手首を捕まれたまま涙がぽろりと頬を伝った。
「泣かないで…ユーリ君。君の笑顔が翳ると、私は…辛い」
「ふ…ぅ……」
秋津が心を込めて謝ってくれることよりも、コンラートが氷のように凍てついた表情のまま、何も言わないでいることが辛くて涙を止められなくなってしまう。
しかし…予想外の光景が有利に抵抗を止めさせた。
ふと見ると、向こうで顔面蒼白になったタイ焼き屋のおじさんが携帯電話を手にしている。
《すわ、男子高校生誘拐か!?》と、通報しかけているのではないだろうか?
「お…おじさんっ!痴話喧嘩ですっ!ホモ同士の痴話喧嘩ですからお気遣いなくっ!!」
「ユーリ…俺はあなた以外にはストレートです」
「俺だってそうだ馬鹿野郎っ!」
不満げなコンラートの顎に頭突きをかましたら、直撃を受けるようなヘマはしなかったが、軽く唇を尖らせてそっぽを向いてしまった。
『この我が儘男…っ!』
それでも好きな自分はどうかしていると思う。
「ユーリ君…私はホモじゃなくてゲイ…」
「違いが分かんないから、どっちでも良いよっ!」
大真面目な顔をして訂正してくる秋津もなかなか大したタマだと思う。偶然小銭を持ってない彼に同情しただけなのに…ひょっとして、エライ人に捕まったのではないだろうか?
とにもかくにも、健全な市民に無用な心配を掛けないよう、別の場所に移動すべきではないだろうか?
「社長、何をしておられるのですか?」
「ああ、佐々野。いや…とても素敵な子がいたんで、口説いていたところだったんだ」
「その美人…」
佐々野と呼ばれた男はちらりとコンラートを見たが、鋭利な視線に晒されて肩を竦めた。
「…の方ではないですね。では、高校生の方?あなた、捕まりたいんですか?平然と青少年育成条例に違反しないでくださいよ」
辟易とした顔をしてゴツンと拳を秋津にぶつけてきたのは、端整な顔立ちをした三十代くらいの眼鏡青年だ。少し明るい色合いの髪は《端然》と《軽快》の中間くらいにセットしてある。
ちょっと掴みどころのない人だ。
「あの…秋津さん、この人は?」
「秘書の佐々野だよ。運転手も兼任してくれてるんだけど…さっきカマ掘られちゃってね。代換車の手配を頼んでたんだ。佐々野、都合ついた?」
「もう来てますよ。先方にも時間変更をお願いしています」
「ふーん…まあ、これ以上は待たせられないか…」
秋津は後ろ髪引かれつつも、何とか仕事を優先させる気になったようだ。
まあ、ここで有利を優先させたらどんなスチャラカ代表取り締まりかと思うが。
…と思ったのも束の間、有利はわっしと両手を捕まれた。
秋津はかなり執念深いタチらしい。
「ねえ、襲ったりしないから…お願いだ。頼むからお礼をさせてくれないか。君に、私って男を知って貰いたいんだよ」
「でも…あの……。本当にお礼なんて良いんで…」
「頼む…この通り!」
今度は両手を頭の上で合わせると、深々と頭を下げて懇願した。
その様子には一種独特のおかしみがあり、有利はさっきまで泣いていたのも忘れてくすくす笑ってしまう。
「…笑ってくれた!やっぱり良い顔だ」
にこ…っと笑った秋津は少年みたいに可愛くて、彼の方こそ良い顔をするものだと思う。この愛嬌があるからこそ、上手くこの不景気の世の中を渡っていられるのかも知れない。
「あはは…じゃあまた来週ここで、なんか奢ってくださいよ。今度はたこ焼き屋が来てると良いな!」
コンラートは軽く睨んでいるが、何となく彼に対する当てつけの気持ちもあって約束を交わしてしまった。
もしかしたら酷くお仕置きをしようとするかもしれないけれど…不条理な行動は、幾らコンラートでもそろそろ自制して貰わなくてはならない。
『だって俺はコンラッドのこと好きだけど、何でもかんでも拘束されたり、振り回されたりするのはゴメンだもん』
好きでいることと支配されるのは違うのだと、今日はじっくり説明してみよう。
そんな風に考えて、有利は秋津に手を振って別れてから、コンラートに向き直った。
→次へ
|